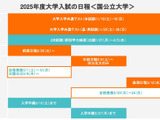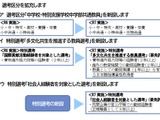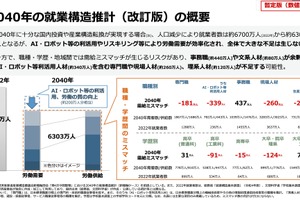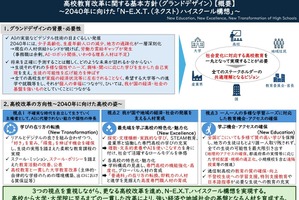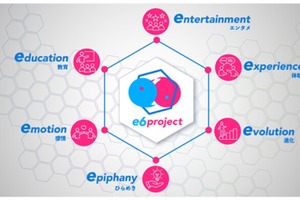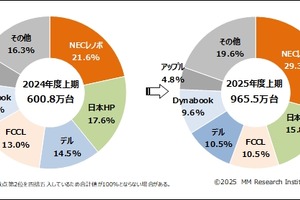さまざまな分野で生成AIの利用が進む中、教育現場でも校務や授業での利活用が議論され、その導入も徐々に進みつつある。だが子供たちの情報を扱う教育現場では「本当に大丈夫なのか」という漠然とした不安もあるだろう。生成AIを安全安心に使うためには、どうすれば良いのか。
教育現場におけるMicrosoft 365のデータ保護や新たな機能、生成AIとの向き合い方などを、日本マイクロソフト パブリックセクター事業本部 公共・社会基盤統括本部 教育戦略本部ソリューションエリアスペシャリストの青木智寛氏と、クラウド&AIソリューション事業本部 モダンワーク統括本部 第3技術営業本部 テクノロジースペシャリストの廣瀬望氏に聞いた。
個人情報漏洩を防ぐ安心のデータ保護機能
--教育現場での生成AIの利用について、どのような声が寄せられていますか。
青木氏:教育委員会や学校の先生から、教育現場での生成AIの利用には不安があり、一歩踏み出せないという声が多く聞かれます。その際に、私たちはまず「2023年7月に文部科学省が示した『生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン』をご確認いただくことが大事」だとお伝えしています。

データの保護に関しては、生成AIの種類によっては入力された情報が生成AIの学習に使われる可能性があるため、ガイドラインには「きちんと見極めたうえで個人情報が流出しない工夫を自治体や学校で講じることが重要」だと書かれています。このような点が、先生方が不安に感じている原因のひとつだと思います。
学校で利用されている組織向けのCopilotは、入力された情報がLLM(Large Language Model、大規模言語モデル)に学習されないようにするデータ保護機能を備えています。そもそも「個人情報を入力しない」というルール作りも必要ですが、機能によってデータが保護されることも大切です。学校で利用されているCopilotの安全性を知り、先生方に安心してご利用いただきたいですね。
廣瀬氏:また、管理者からは「どのように利用されているのか」「正しく使われているのか」という不安の声も聞かれます。そのため、学校で利用されているCopilotには、利用状況や誰がどのように使っているかを管理者が把握できる仕組みも備えました。
安全に使えることを知ることが活用への第一歩
--AIに関する研修の反響はいかがですか。また、研修ではどのようなことが学べるのでしょうか。
青木氏:AIに関する研修は人気が高いですね。マイクロソフト社員による研修も行っていますが、パートナー企業も含めると非常に多くの研修を行っています。
研修ではまず、前提知識を揃えるために「生成AIとは何か」から始めます。そして、生成AIは大量のデータからパターンを学習し、それに基づいてさまざまな可能性から選択して回答を生成するため、回答が確率的なものであるという特性について。さらに、学校現場での具体的な活用方法についてお話ししています。
そして、多くの方が不安に感じている個人情報の漏洩や著作権侵害については、学校で利用されているCopilotでは入力データが保護されること、利用者が意図せずに著作権を侵害するものを生成した場合にはマイクロソフトが訴訟のサポートをすることを伝えています。
--教育現場でのCopilotの活用状況はいがでしょうか。
廣瀬氏:業務や授業に活用される先生も少しずつ増えてきていますが、やはり使い始めに壁があると感じています。「これを使って良いのかな、大丈夫なのかな」と考えて、なかなか使い出せないという先生がかなり多い印象です。

青木氏:ご自身でCopilotの使い方を試行錯誤している先生の中には「自分の使い方は本当に正しいのか」という不安がある方もいらっしゃると思います。研修では安全面の情報を求める先生が多いです。
研修に参加して、Copilotが安全に利用できることを知った先生からは「意図せずルールから外れてしまう可能性もあるので、情報漏洩しない仕組みがあることで安心できる」という声が聞かれたり、「実際に使ってみたら難しくなかった」という先生も少なくないので、安全面や使い方に心理的障壁があるように感じています。
--安全に使えることを知ることが活用への第一歩ですね。データが保護されている状態であることを確認するにはどうしたら良いのでしょうか。
青木氏:組織向けのCopilotを開くと「緑の盾マーク(シールドのマーク)」が出てきます。それがデータは保護されているという証です。先生がCopilotを利用する場合は、個人用アカウントではなく、学校や教育委員会で配布されている、Microsoft 365 Educationのアカウントからログインして、Copilotの盾マークを確認してください。
廣瀬氏:盾マークにマウスのポインタをのせると「エンタープライズデータ保護」という文字も出ますので、その文字をご覧いただけばさらに安心かもしれません。

利用状況を把握できる新機能
--アップデートされた機能について教えてください。
青木氏:Copilotを使い始めた教育委員会から、今後の施策を考えるうえで、先生たちの利用状況を知りたいという相談が多く寄せられていました。そこで組織向けCopilotでは、情報閲覧に関する機能を2024年9月にアップデートしました。
廣瀬氏:組織のアカウントでサインインしていれば、いつCopilotを利用したかが「監査ログ」に記録されます。教育委員会はそれを見れば、先生方がCopilotをどのくらい利用しているかがわかります。また、どんなプロンプトを入力して、どのような回答が返ってきたかという履歴も管理者側で見ることができるのです。さらにCopilotにおけるプロンプトとその応答を長期間、保持しておくことも可能で、従来よりもコンプライアンスに対して堅牢な機能が備わったと言えます。
--データ保護機能や監査ログ、プロンプトなどのログの保持は、どのパッケージで利用できるのでしょうか。
廣瀬氏:教育機関向けのライセンスであるMicrosoft 365 EducationにはA1、A3、A5と3つのグレードがありますが、このすべてのグレードでデータが保護されるCopilotを無料で使うことができます。監査ログの閲覧もすべてのライセンスで可能です。ただし、プロンプトなどのログの保持はA3、A5ライセンスのみとなります。
青木氏:A3以上のライセンスを所有しているにもかかわらず、プロンプトなどのログの保持ができることをご存知ない自治体も多いようなので、ぜひ積極的に使っていただきたいと思います。
--ほかにはどのような新機能がありますか。
青木氏:従来のCopilotは、テキストで聞いてテキストで回答する形式のみでしたが、ファイルのデータを取り込んでグラフを作るといったことができるようになりました。Copilotは画像ファイルや、Word・Excel・PowerPoint、テキストファイル、CSVファイル、PDFなどの取込みに対応しています。普段、先生が使っている形式のファイルはほとんど取り込むことが可能です。
廣瀬氏:CopilotがLLMで対応しきれない回答は、検索エンジンのBingから情報を補完する仕組みになっています。ただ、Bingに個人名などを入力したら学習されてしまうのではないかと不安に感じる場合もあるでしょう。そこで、BingとCopilotを連携できないように設定することができるようになりました。
実際にはCopilotとBingを連携する際にはプライバシー保護に配慮する仕組みがありますが、不安な場合は管理者モードでBingとの連携を切ることで、AIがすでに学習した内容は回答するが、学習していないものは回答しないという状態に設定できます。
Copilotをみんなで使って活用を広げる
--Copilotを教育現場でどのように活用してほしいですか。
青木氏:たとえば、Teams上にCopilotの情報を共有するためのチームを作って、そこで「こんな使い方できたよ」「こんな風に使ったら効果的だったよ」と先生方が気軽にコミュニケーションしながら活用を進めていただきたいです。1人で悩まずに、わからないことがあれば先生同士で助けあい、一緒に学びを深めながら活用を進めてほしいと思っています。そのために、マイクロソフトも研修などでサポートしていきます。
廣瀬氏:プライベートで生成AIを使いこなしている若い先生も多いと思いますので、その発想を生かしてほしいと思います。そのためには、ベテランの先生にも理解していただくことが必要です。若い先生の発想と、ベテランの先生の経験が融合すれば、より効果的な使い方も発見できるのではないでしょうか。
--使い方のコツを教えてください。
廣瀬氏:Copilotに、思いついたことを何でも聞いてみてほしいです。聞いてみて思ったような回答が返ってこなくても、諦めずに聞いてみてください。生成AIは進化が速いので、少し前にできなかったことが数日後にはできる場合もあります。
また、言い方を変えてみるのもコツのひとつです。たとえば、人に「喉が乾いた」と伝えるだけでは何が出てくるかわかりません。でも「つぶつぶの入ったオレンジジュースが飲みたい」とか「微炭酸が良い」とか、具体的に指示をすれば欲しいものを明確に使えられますよね。それと同じで、Copilotにも何を知りたいのかを具体的に伝えられるよう、言い方を考えてみると良いと思います。
先生同士で教えあったり、子供からアイデアをもらったりしても良いでしょう。マイクロソフトは学校で利用する際に不安や懸念を払しょくする仕組みを作っています。今後も安心安全にCopilotを使っていただくための情報を教育現場にしっかりとお届けしたいと思います。
組織アカウントでログインしたCopilotならば、利用する側のデータが保護され、さらに管理する側も監査ログやプロンプトの保持などでセキュリティ対策を講じられる。ぜひAIを味方にして、より良い教育に進んでほしい。
Microsoftの生成AI 明日から使えるCopilot依頼文(プロンプト)10ダウンロードはこちら※ボタンをクリックすると資料のダウンロードを開始します。