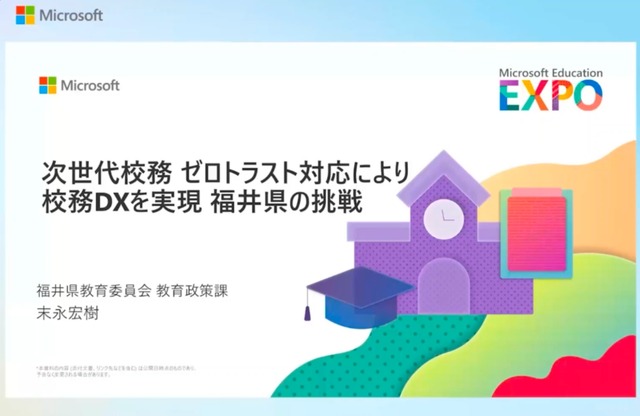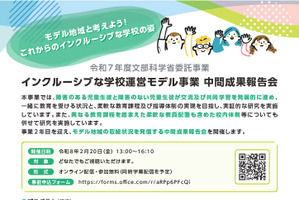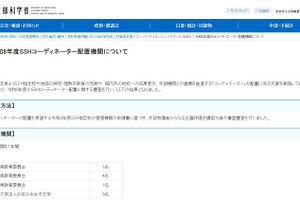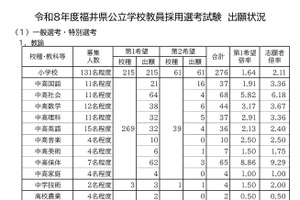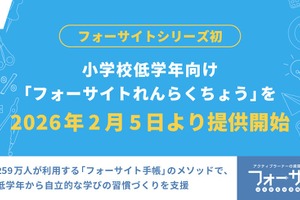2025年2月13日にオンラインで開催された「Microsoft Education EXPO 2025」。生成AI活用や次世代校務のDX化など先進的な取組みを行う教育委員会や学校の教職員が登壇し、実践事例を紹介したほか、現場の教育環境をさらに向上させるMicrosoft Educationの多様なソリューションが活用例を交えて紹介された。
福井県教育委員会の末永宏樹氏は「次世代校務 ゼロトラスト対応により校務DXを実現―福井県の挑戦」と題した講演に登壇。県立高校の校務支援システム更改への取組み、そして今後の展望について紹介した。
閉域網の限界による教職員の負担
末永氏は冒頭、現行の校務基盤の課題について言及。福井県もほかの多くの自治体と同じく閉域網型の環境であり、外部からのアクセスが制限されていることが課題だと語った。そのため、自宅や出張先など校外からのリモートアクセスが困難で、教職員は基本的に端末の持ち出しができずテレワークができない、といった課題が顕著にみられたという。
「特に、コロナ禍をはじめとする緊急時の対応が極めて難しく、現場の教職員の負担が大きくなる要因のひとつとなっていました」と末永氏は振り返る。おもな課題は閉域網型の環境であることに起因していることから、福井県では現行踏襲せず新しい環境整備へと踏み切ることを決めた。
ゼロトラスト型校務基盤への転換、文科省の方針と県の決断
福井県が閉域網型の現行環境を見直し、新たに構築を目指した校務基盤。それが、従来の境界の概念を取り払い「あらゆるアクセスを信頼せず、安全性の確認を行う」というセキュリティの考え方に基づくゼロトラスト型環境の導入であった。決断の背景には、文部科学省がゼロトラストによる次世代校務環境を推奨していたこともあった。
「ゼロトラスト環境が推奨される中で、利便性とセキュリティを両立できるか、またコスト面で実現は可能かを慎重に検討しました。結果として、ゼロトラスト型の校務基盤は福井県の求める要件に合致しているとの判断に至りました」と、末永氏は移行に踏み切った経緯を説明した。
新しい校務環境がもたらす働き方改革
ゼロトラストの新環境は、安全性を確保しつつ、どこからでも校務可能な環境を実現し、教職員の働き方改革に大きく寄与すると末永氏は見込んでいる。ゼロトラスト型の校務基盤の実現で課題であったネットワークの境界はなくなり、適切な手順を踏めば、自宅や出張先、職員室以外の校内のさまざまな場所でも業務にあたることができるようになる。
新環境では業務にあたる場所の制限がなくなることについて末永氏は、「働き方を柔軟にすることで、教職員が本来の業務に集中できる環境を整えることが何より重要であると考えました」と話す。福井県では教職員の働き方変革を進めるうえで、ハード面(インフラ・システム)の整備を優先した。教育委員会が先頭に立ってハード面を強力に後押しし、環境が構築された後にソフト面(運用・活用)の改革を進めるという方針が取られているという。
Microsoft 365 A5を中核としたゼロトラスト基盤
今回、福井県が構築した新環境の核となるのがMicrosoft 365 A5である。ゼロトラストのセキュリティ基盤およびアカウントのベースとして活用できる、セキュリティ機能を含む包括的なソリューションであることが採用の決め手となった。
また、検討の初期段階ではA3にソリューションを組み合わせて似たような構成にすることも考えたが、将来的な拡張性とアップデートの継続性、シンプルな構成で移行や再構築の負担を軽減できるといった点から、A5の採用を決めたという。
一方で、 Microsoft 365 A5ではマイクロソフト以外の範囲については制御ができない部分があり、学校ではマイクロソフト以外のサービスも用いられていることから、Microsoft 365 A5とほかのセキュリティ製品を組み合わせる形で高度なセキュリティ基盤を実現した。結果として、マイクロソフトのサービスであるTeamsやSharePointに加え、必要に応じて一部他社のクラウドサービス(GoogleやAWSなど)も開放可能になった。
また、同時に教職員用端末としてSurface Laptop Goを調達。マイクロソフト環境との親和性を最大化すると共に、技術サポートサービスであるユニファイドサポートを活用し、教職員専用のサポート窓口を設置するなど、マイクロソフト製品をトータル活用し、次世代校務環境のDX化を推進していくと末永氏は語る。
Power Platformを活用したローコード開発への展望
さらに福井県では、SharePoint Onlineを活用し、全教職員が閲覧できる共通のポータルサイトを構築。ポータルサイトからマイクロソフトのソリューションへの動線を設けたり、ヘルプデスクへ直通でつながるAIチャットボットを組み込んだりと、利便性を重視した環境整備も進められている。これらは完成形ではなく、実際に使用していく中で、現場の先生方の要望を踏まえてカスタマイズしながら運用を進めていく方針だという。
また、マイクロソフトが提供するローコード(※)開発ツール「Power Platform」を活用し、校務のDX化をさらに推進する計画がある。従来、校務ではマクロなどソフトウェアの自動化が限定的であった。今後はPower Platformを活用することで、柔軟な業務プロセスの改善が可能になる。
※ソースコードの記述を最小限に抑えてアプリケーション開発をする手法。「ただし、Power Platformの利用には機能や使い方に関する知識が必要となるため、すべての教職員がすぐに活用できるわけではありません。Power Platformの利活用に関する研修など、来年度以降はソフト面に関する研修も段階的に実施し、活用を広げていきたいと思っています」と末永氏は語った。横展開しやすいというPower Platformの特長を生かし、学校間での業務の標準化やナレッジの共有を積極的に進めることで、福井県における教育現場のDXがさらに加速することが期待されている。
DXは整備が「ゴール」ではなく「運用のスタート」
末永氏は、今回の校務DX推進において「環境整備はあくまでスタート地点」であると強調した。以前は、システムを構築すればひと段落という風潮があったが、環境を整備したうえで、新しい機能やソフトウェアを教職員が使いこなせるようになる、実際に運用してもらうことこそが重要だと考えている。
「クラウドベースの環境では、継続的な運用と改善が重要です。今後は、教職員の研修、フィードバックを反映したシステム調整、サポート体制の充実などを通じて、校務DXの定着を図っていきます」と末永氏は語る。
利活用のハードルを下げるデジタルの進歩
昨今は教育現場に限らず、 DX人材不足が叫ばれている。福井県においてもDXに関する人材は不足しており、人材確保に苦労しているのが実情だという。学校現場に目を移すと、それはより顕著な問題になっている。高校では「情報」の授業が必修科目となったが、授業ができる教員は少なく、万全な授業環境を構築できる人材は特に貴重だ。
一方で、利用する側に立つと、デジタルの進歩により従来のような専門的知識を必要とせずともさまざまなソリューションの利活用ができる状況にある。末永氏は「基盤を構築するまでは苦労が多いですが、実際構築してしまえば、先生方の利便性や校務のDX化が非常に進みやすくなると確信しています」と述べ、全国の教育委員会や教職員に向け力強いメッセージを送った。こうした事例の共有などを通して、互いに切磋琢磨し、次世代校務のDX化が全国の教育現場で進んでいくことに期待が寄せられるセミナーとなった。
福井県の挑戦は、文部科学省が示す次世代校務DX化の先進事例として全国の自治体にも多くの示唆を与えるものであった。今後、より柔軟で安全な校務環境が教育現場に定着し、教職員が本来の業務に集中できる環境が整うことが期待される。
ゼロ トラストで推進する次世代教育のセキュリティMicrosoft「AI Skills Navigator」