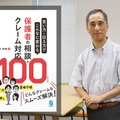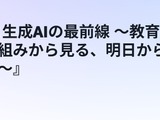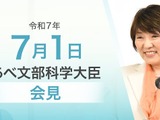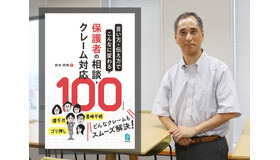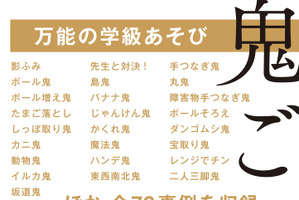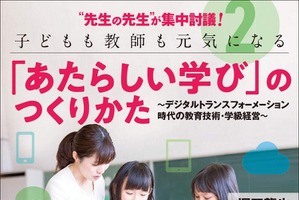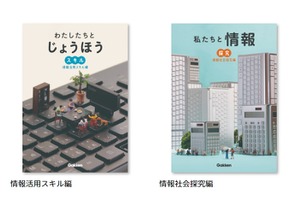リシードで人気の連載「相談・クレーム対応Q&A」シリーズがこの度、学事出版社より書籍として刊行された。著者の鈴木邦明氏に、この連載や書籍化にあたっての思いを聞いた。
社会状況の変化を反映した構成に
--『言い方・伝え方でこんなに変わる 保護者の相談・クレーム対応100』の刊行、おめでとうございます。まずは、本書の概要についてお聞かせください。
本書は、リシードでの連載をもとに書籍化したものです。連載記事数は2025年5月末時点でも230本あり、書籍化にあたって内容を整理・再構成しました。
基本的な内容の追加はありませんが、似たようなテーマの記事をまとめたり、社会状況に合わなくなった内容は除外しました。特にコロナ関連の記事は、マスクの着用や距離の取り方など、現在の状況にそぐわない内容が多かったため、大部分をカットしています。
リシードでの連載記事は、公開後2~3年経過しても定期的に読まれているものもあると聞いています。保護者対応や学校での出来事など、特定の問題が発生した際や、文部科学省からの通知が出された際などに、過去の記事が参考資料として活用されるのではないかと考えています。
教育現場では、同じような課題が繰り返し発生します。地域によって大きな問題として取り上げられることもあれば、表面化しないこともあります。こうした状況に対して、適切な情報提供を続けることが重要だと考えています。
若手教員の増加を踏まえて
--本書は先生向けにまとめられています。どのような先生に手に取ってもらいたいとお考えですか。
特に若手の教員に読んでもらいたいですね。近年、教員採用に積極的な自治体・学校が増え、若い教員の数が増えています。
若い先生は、子供たちと一緒に遊んだり、デジタル機器を使いこなしたりと、柔軟な対応ができるのが良い面ですよね。50代の教員には体力的に難しい校庭での遊びも、若手教員なら積極的に取り組めます。ただ、保護者対応については経験値が必要なため、苦労している先生が多いのが現状です。
実際、教員の離職理由の上位には保護者対応の困難さがあげられています。大学の教職課程で学ぶのは教科教育が中心で、保護者対応などの学級経営については実習で触れる程度です。しかし、実際に担任になると、自分より年上の保護者30~40人を相手にしなければならず、戸惑う先生が多いのです。
保護者対応の困難さは、何も若手の先生だけの問題ではありません。10年以上のベテラン教員でも、突然メンタル面で休職せざるを得なくなるケースも増えています。ですので、そうなる前に、解決のヒントを探すためにもこの本を読んでほしいと考えています。
教員と保護者の良好な関係構築のために
--本書に込めた想いについてお聞かせください。
本書の根底にあるのは、教員と保護者の良好な関係構築への願いです。教員と保護者の関係が良好であれば、たとえトラブルがあったとしても、それが子供の成長の機会となり得ます。しかし、関係が悪いと些細なことが大きな問題に発展してしまう危険性があるのです。
現在は教員と保護者の直接的なコミュニケーションの機会が減少しています。特にコロナ禍中は授業参観やその後の懇談会などの場が設けられず、コロナ禍が明けても以前のような形に戻り切れていません。また、セキュリティの強化の影響や、教員が多忙になったことが知られるようになり、保護者側に遠慮があることも考えられます。
--そうした課題を解決するためには、具体的にはどのようなことが必要だとお考えでしょうか。
ICTの活用がひとつの解決策になると考えています。たとえば、メールやアプリなどのツールを活用することで、働く保護者でも24時間いつでも連絡が可能になります。たいていの学校は学校Webサイトを開設していますから、トップページの見やすいところに問合せ先メールアドレスを記しておけば良いのです。しかし、自治体によって対応に大きな差があるのが現状で、メールアドレスすら公開していない学校もあります。
とある小学校の校長先生にメールアドレスの掲出の件をアドバイスしたところ、「問合せが増えて収拾がつかなくなる」という懸念の声をいただいたことがあります。しかし私は、むしろ適切な情報共有ができないことで、より大きな問題に発展するリスクがあると考えます。
学校への要望や相談がしづらい環境だと、保護者の些細な疑問が解消されないまま不信感が蓄積してしまいます。その結果として、対応が遅れ、より深刻な問題に発展する可能性があるのではないかと思うのです。
確かにさまざまな連絡が来ることは予想されます。しかし、現代社会において、企業でも行政でも、メールによる問合せ窓口の設置は当たり前になっています。必要な情報を適切に選別し、重要な案件に対応する体制づくりが学校でも重要なのではないでしょうか。
「ハインリッヒの法則」を応用した予防的アプローチを
--鈴木先生がお考えになる「保護者対応のポイント」とはどんなものでしょうか。
先ほどの話にもつながりますが、保護者対応で重要なのは、信頼関係の構築と早期対応だと思います。その際に参考になるのが、産業事故防止で知られる「ハインリッヒの法則」の考え方です。
大きなクレームは突然発生するわけではありません。たとえば、「新聞紙を持ってきてください」という指示に対して、「新聞をとっていないのだけどどうするべきか」という疑問が保護者の間にあったとします。もしもこの段階で保護者が相談ができる環境にあれば、「使用用途は○○なので代用となる紙を持たせてください」と伝えるなど、適切に対応できるでしょう。そのためにはやはり、保護者が気軽に質問や相談ができる環境づくりが重要なのです。
また、「モンスターペアレント」という言葉の使用には慎重であるべきだと私は思います。保護者の激しい反応の背景には、学校側の対応に不備がある場合もあります。保護者を一方的に非難するのではなく、双方向のコミュニケーションを心がけることが大切なのではないでしょうか。
現場の声を反映した記事作り
--最後に、読者へのメッセージをいただけますでしょうか。
読者の方々からの反応や質問が、新しい記事のヒントになっています。現場で悩む先生方の役に立てることを願って、これからも発信を続けていきたいと思います。教育現場は今、離職者の増加やICTの導入、コロナ禍の影響など、さまざまな変化に直面しています。本書が、そうした課題に向き合う教員たちの一助となることを願っています。
--ありがとうございました。
『言い方・伝え方でこんなに変わる 保護者の相談・クレーム対応100』読者プレゼント
鈴木邦明先生の『言い方・伝え方でこんなに変わる 保護者の相談・クレーム対応100』を、抽選で5名にプレゼントする。
応募方法:下記のボタンより応募する
応募締切:2025年8月20日(水)
当選発表:商品の発送をもってかえさせていただきます
※応募にはリシード メンバーズ(リシード メンバーズとは)への登録(名前とメールアドレス)が必要です(登録手順)。ご登録のうえログインし、下記「応募フォーム」ボタンをクリックしてお申し込みください。