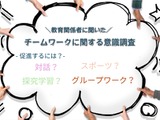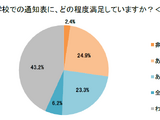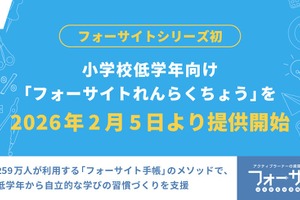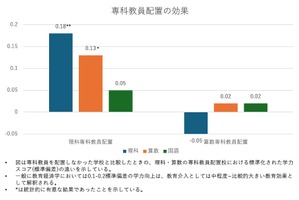学校に寄せられるさまざまな相談やクレーム。保護者や地域からのクレームに先生はどのように対応するのが良いだろうか?クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第239回のテーマは「非認知能力を高めてほしい」。
非認知能力とは?
「非認知能力」とは、学力テストや知能テストなどで測ることができない「内面的、社会的スキル」を指します。具体的には「自己肯定感」「忍耐力・自己抑制力」「共感力・思いやり」「感情のコントロール」「意欲・やる気」「協調性・コミュニケーション能力」「問題解決力・主体性」となります。コロナを経て、社会が大きく変化している現在、こういった能力の大切さが指摘されており、学校でも非認知能力の向上に力を入れてほしいという訴えをしてくる保護者もいます。
コロナを経て、社会の仕組みが大きく変わりました。そういった中でも特に「人との関わり」は大きな変化がありました。2020年、2021年には「三密を避ける」ことが推奨され、人と人の間に物理的な距離ができました。その後も、マスクを着用した生活が、子供の成長に影響があるのではと指摘されていました。学校におけるGIGA端末や家庭におけるスマホなどのデジタル機器が子供のそばにあることによる影響も考えられます。ICT機器には利点もありますが、欠点も存在します。何かが悪く、何かが良いという単純なものではなく、現状においてどういったバランスで取り組んでいくのかということが大切になってくるものでしょう。
子供の自殺と自己肯定感
ところで、残念ながら、子供の自殺者数が高止まりしていることなどは、そういったことが関係していると思われます。子供の自殺について調べてみると、先進7か国(G7)の中で、子供世代の死因の1位が自殺なのは日本だけです。また、OECD諸国において、コロナ以降、子供の自殺者が増えているのは、日本と韓国だけということです。
自殺とも関連のある「自己肯定感」に関して、日本の子供は、とても低い数値となっています。国際比較において最低レベルとなっています。ベネッセ教育総合研究所(2015年)による日本・中国・韓国・アメリカの比較では「自分に満足している」は日本7.5%、米国50%超、「自分には長所がある」は日本32.9%、米国89.7%となっています。日本の子供の自己肯定感の低さについては、失敗を認めにくい風潮、同調圧力、親の過干渉・過保護などがあるとされています。
認知能力と非認知能力をバランスよく育てていく
非認知能力に関しては、たくさんの研究がなされています。「ペリー就学前プログラム」というものがアメリカで1960年代に行われています。幼児期に良質の保育、教育を受けた子供はその後、さまざまな面(学歴、雇用、収入、犯罪率など)でプラスの影響があったというものです。
学校においては、さまざまな取組みで非認知能力の育成を目指しています。生活科や総合的な学習、探求学習などがそういったものです。さらに、日々の係活動など、さまざまな場面で非認知能力の育成に取り組んでいます。非認知能力は、子供の習い事(塾など)では育成が難しいものです。学校は、その仕組みにおいて、意図的、計画的に総合的な子供の育ちを目指しています。「認知能力」「非認知能力」とも、バランス良く育てていくことが望まれます。
本企画では、読者の皆さまからの質問を受け付けています。下記のボタンをクリックして表示されるフォームより送信ください。実際に学校へ寄せられた相談のほか、保護者が学校へ伝えた相談など、鈴木先生に対応方法を聞いてみたい相談事例を募集します。
質問をする