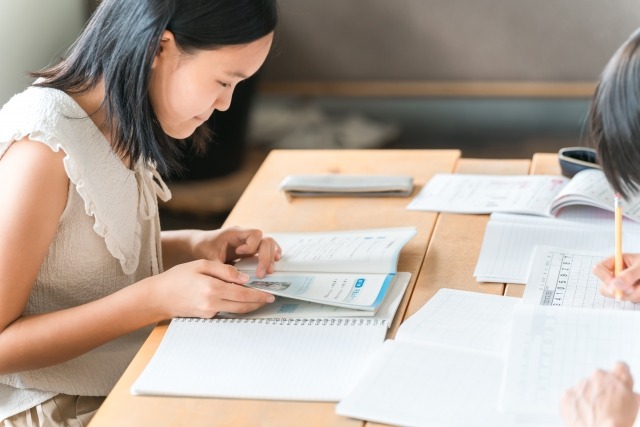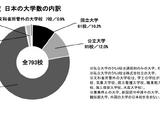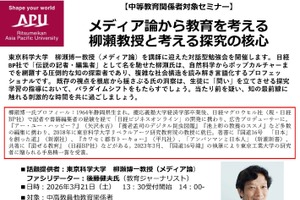学校に寄せられるさまざまな相談やクレーム。保護者や地域からのクレームに先生はどのように対応するのが良いだろうか?クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第238回のテーマは「宿題を無くしてほしい」。
宿題の意味とは?
宿題に関しては、このコーナーでこれまでに何回も話題にしています。たとえば、量が多い・少ない、内容が難しい・易しい、個別対応をしてほしい、GIGA端末で取り組めるものにしてほしいなどをこれまで記事にしてきました。親にとってはとても関心の高いテーマなのだと思います。
多くの場合、宿題は全員に一律に課すものです。そういったやり方が日本の学校では一般的でした。ただ、社会のさまざまな部分が変化している中、「一律で課題を課す」ということの意味を考える時期に来ているのではと私は思っています。日本が高度経済成長期にあり、効率よく質の高い工業製品などを作っていくということが大切な時代は「全員一緒」「揃える」ということが今以上に大事だったのでしょう。今は状況が色々と変わってきています。普段の授業においても「個別最適な学び」が大切にされています。GIGA端末を適切に使うことで、個に応じた学びがとてもしやすくなりました。そういった状況においては、宿題も「一律に」というやり方も考えていく必要があるのでしょう。
一般的に、宿題は「考える」というものよりも「作業的なもの」が多い傾向にあります。「漢字ドリル」や「計算ドリル」などがそれにあたります。子供の育ち(学び)のためというよりも「宿題をやること」が目的となっている場合もあります。
宿題に取り組むメリットは一般的に「学習の定着」「学習習慣の定着」などがあります。ただ、子供にとっても、教員にとっても、保護者にとっても負担(負荷)になっている場合もあります。取り組み方にもよるのですが、取り組む際のエネルギーに対して、効果が少なくなっていることもあります。効率の悪い学びということになります。
宿題を無くすメリット
宿題を無くすことで「自主的な学びが促進される」「家庭との時間が増える」「子供のストレスが減る」などがメリットとされています。宿題を無くしたことで勉強をしないということではなく、自分の興味に応じた取組みをしていくことが望まれます。特に夏休みなどの長期休業期間は普段の学校教育では体験できないものに触れることができます。これまでも取り組まれていた絵画、作文、自由研究などのコンテストについては、学校の役割はそれらを紹介する程度で良いと思います。何に取り組むのかを決めたり、提出したりするのは家庭の役割として対応としていくことで良いでしょう。やる気のある子供(家庭)はどんどんチャレンジしていけば良いと思います。
ところで、実際に宿題の無い学校もあります。長野県佐久市立浅間中学校は原則として宿題を無くすという方針で取り組んでいます。学力が低下したということはなく、自分で学ぶ力が付いたのではと考えられています。現状、宿題を無くしたという学校はまだわずかです。ただ、GIGA端末の活用などと関連して、宿題の取組み方についてそれまでとは変えている(変えようとしている)学校はたくさんあるようです。子供の学び(育ち)のために何が良いのかということをしっかりと考えていきたいです。
本企画では、読者の皆さまからの質問を受け付けています。下記のボタンをクリックして表示されるフォームより送信ください。実際に学校へ寄せられた相談のほか、保護者が学校へ伝えた相談など、鈴木先生に対応方法を聞いてみたい相談事例を募集します。
質問をする