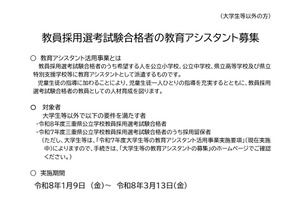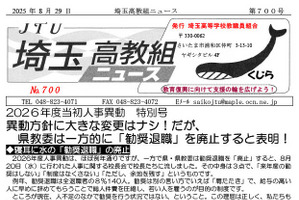学校に寄せられるさまざまな相談やクレーム。保護者や地域からのクレームに先生はどのように対応するのが良いだろうか?クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまなクレームに対応する際のポイントを聞いた。第250回のテーマは「クマが出没しないか不安」。
全国各地でクマが出没
日本中のいくつもの街でクマが出没し、さまざまなトラブルが発生しています。これまでもなかったわけではないですが、今年は特に多く、このところ毎日のように報道されています。2025年10月3日現在で死者が7人、4月から8月の人身被害者も69人と過去最高のペースとなっています。山のエサが不作となっていることやクマが人の居住地にエサとなる物があることを学んだことなどが原因だとされています。クマの出没を不安に感じている子供や保護者も一定数いることでしょう。
このことに関して、学校に相談などがあるかもしれません。学校での対応を検討する必要が生じます。私は「教職員が子供の登下校に付き添い、安全確保をする」というやり方には反対です。クマと遭遇するかもしれないという状況で、丸腰の教職員が子供に付いて行ったとしてもできることはほとんどありません。もしクマと遭遇してしまったら、教職員は子供とクマの間に入るはずです。真っ先に逃げてしまうようでは大問題になってしまいます。そういった際に教職員ができることはクマスプレーを使って抵抗することや自分が盾になりながら子供に逃げるように指示をすることなどでしょう。最悪のケースも十分に考えられます。警察や猟友会などの武装をした人であれば、クマと遭遇した時にもできることがあります。教職員は装備もありませんし、専門の訓練も受けていません。そういった状況で安易に教職員の付き添いなどはしない方が良いと私は考えます。これは類似の他のケースでも同様だと思います。イノシシなどが出没したケース、拳銃や刃物を持った犯罪者が逃走しているケースなどです。
登下校の責任は保護者にある
自宅から学校までの登下校の責任は基本的に保護者にあります。登下校に関することは、学校保健安全法で定められています。学校保健安全法第27条・第30条では、学校や教師の果たす役割について「登下校の際の交通安全のルールを教えること、警察や保護者と連携をすること」とされています。また地域の治安維持、安全の確保などは、警察や行政などに責任があります。そういったことを踏まえると、教師が登下校の付き添いをするということではなく、自家用車などで家族が送迎することを依頼することの方が望ましいでしょう。車を止める場所について問題となることもありますが、特別に校庭も使用可能とすることで、たくさんの車が来た場合でも対応可能でしょう。また、自治体が特別にバスなどを確保するやり方もあるでしょう。
それと共に、安全確保に関しては、警察などに依頼をしていくことが望まれます。クマの問題は子供の通学の問題だけではなく、地域住民すべての人に関わる問題です。警察や行政も積極的に動いてくれると思われます。今回のクマの件だけはありませんが、子供に関わるすべてのことを学校だけでやっていこうとするやり方は変えていく方が良いと思います。世の中にある最適な人的資源を有効に活用していくことが望まれるやり方でしょう。
本企画では、読者の皆さまからの質問を受け付けています。下記のボタンをクリックして表示されるフォームより送信ください。実際に学校へ寄せられた相談のほか、保護者が学校へ伝えた相談など、鈴木先生に対応方法を聞いてみたい相談事例を募集します。
質問をする