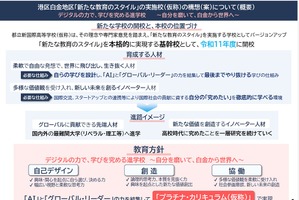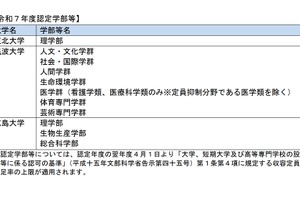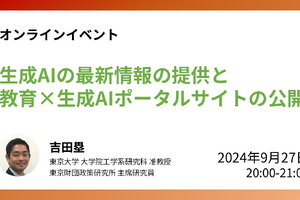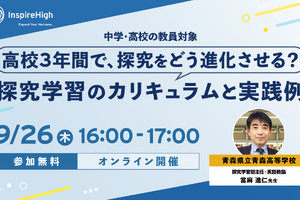リシードは2024年9月19日、中学・高校の経営層や教員をはじめ、教育関係者を対象としたセミナー「世界で勝負できる日本人の育て方」をピアソン・ジャパンと立命館アジア太平洋大学(APU)と共同で開催。アメリカの名門「アイビーリーグ」の一角・コロンビア大学で理事を務める花沢菊香氏を講師に迎え、セミナーを開催した。
本記事ではその一部をレポートする。
19歳で渡米、アメリカンドリームを成し遂げた花沢菊香氏
花沢氏は高校まで日本の一条校で教育を受けたあと、19歳で渡米。コロンビア大学の語学学校で開催されていたサマースクールへの参加をきっかけに、現地で友人をつくり、流行の音楽を聴き、わからない言葉に出会うたび辞書を引きながら英語力を身に付けていったという。
コロンビア大学、ハーバード大学ビジネススクールを経て、ニューヨークでファッションブランド「VPL」を立ち上げ、CEO(最高経営責任者)に就任。「VPL」はアップサイクル*素材を使用するなど、いち早くサステナブルなコンセプトを取り入れ、レディー・ガガやマドンナ、リアーナ、ビクトリア・ベッカムらセレブたちにも愛用される人気ブランドとなった。
また、花沢氏は慈善事業家・社会起業家としての顔ももち、東日本大震災後にはファッションを通じて義援金を寄付する非営利団体「ファッション・ガールズ・フォー・ヒューマニティ(FGFH)」を設立。コロナ禍では世界中どこからでも型紙をダウンロードして医療防護服を自分で縫える仕組みを作るなど、慈善事業にも意欲的に取り組んできた。
さらに、現在は世界を舞台に活躍する日本人をつなぎ、英語で紹介するサイト「THE IROHA」の運営も手がけるほか、9月にはメルカリの社外取締役にも就任し、活躍の場を広げている。
*アップサイクルとは? 本来であれば捨てられるはずの廃棄物にデザインやアイデアなど新たな付加価値をもたせ、新しい製品を作り出すこと。

グローバルな視点から見える日本の教育の課題とは
冒頭で花沢氏は、日本の教育について「初等・中等教育は国際的にも非常に学力が高く、これについて何か問題があるとは思わない。さらに今は探究学習も取り入れられ、学びの幅が広がっているのは良いことだと思う」と評価。一方、アメリカの名門大学で理事を務め、グローバルな起業人材の育成にも携わる第一人者の立場から、次の4つの課題を提起した。
エンダウメント(寄付金基金)設立の必要性
まず指摘したのはファイナンスの課題だ。「高齢化と人口減少の進展で日本の経済は減退しつつあるものの、長年の経済活動によって金融資産は依然として豊富にある」とし、「次世代のより良い教育につなげていくためには、こうした日本の膨大な金融資産を有効活用し、エンダウメントの設立を教育機関や国として考えていくべき」と語った。
エンダウメントとは、教育機関が運営する寄付金基金のことで、花沢氏が理事を務めるコロンビア大学では148億ドル(約2兆2000億円)規模のエンダウメントを運用しており、この運用益によって優れた研究者や教員を採用したり、多様な人材に対して奨学金を供与したりすることが可能になっているという。「今後、国際的な競争力を強化するためには、日本の教育機関でも基金運用益で学校運営をまかなっていくスタイルが重要になってくるのではないか」と花沢氏は指摘した。
理系教育への偏重
2つ目は日本での理系教育への偏重について、花沢氏は「参考にすべき国はアメリカだけではない」と言い、その一例としてフランスをあげた。フランスも、かつては十分な内需に恵まれたこともあって、多くの人々が英語を話さず、むしろ言語の壁をつくることで自国文化を守ってきた。ところが、この保守的な姿勢によって、グローバルに広がった急速なIT化の波に乗れずにいたという。
ところが21世紀に入り、小学校から自国の文化芸術を教えるリベラルアーツ教育を開始。花沢氏は、「20年を経て今、世界一の富豪ベルナール・アルノーが率いるLVMHグループはその教育の成果だ」と語る。LVMHグループといえば、お酒やフレグランス、化粧品、時計、バッグなど、さまざまな高級ブランドを買収して拡大した巨大コングロマリットだ。メイドインフランスは少なく、製造の大部分は他国に委託しているものの、デザインやブランディング、マーケティングなどビジネスの根幹はフランス国内で掌握し、グローバルブランドとして成長させている。
「日本は戦後、自動車や電化製品が経済をけん引してきたため、政府やメディアは理系教育を重視しがちだ。理系に偏重した論調や思考だけではなく、文化・芸術の分野にも、グローバルブランドになり得るお宝がまだたくさん眠っている。」と花沢氏。
「コロンビア大学にはコロンビアコアといって、1~2年生の間にリベラルアーツを学ぶカリキュラムがある。私自身も、そうして大学時代に幅広く学んだ知識は、今でも仕事におおいに役立っていると感じる。AIが加速度的に進化していく時代にこそ、アートや音楽、文学、哲学など、むしろ人にしかできないことの知識が長い目で見て大事になってくるのではないか」と訴えた。

日本が世界に誇れるものを生かすという意識の希薄
3つ目は、日本の教育現場が足元にある強みを生かしきれていないことだ。
「たとえばアメリカ・カリフォルニア州は日本とほぼ同じ広さだが、カリフォルニアが世界に誇れるものといえば、映画やIT、自動車、飛行機、ロケットなど数えられる程度であるのに対し、日本には高度経済成長を支えてきた製造業以外にも、全国津々浦々を見渡せば、数えきれないくらいある」と花沢氏は言う。特に地場産業や伝統工芸などは、地元の人々にとっては身近過ぎる存在だけにその価値に気付けず、「灯台下暗し」になりがちだ。
「参勤交代の時代あたりから受け継がれ、ふるさと納税に代表される農業や食、美術、建築、漫画、アニメ、長寿を実現するライフスタイルや生き甲斐といった概念まで、日本が世界に誇れるものはまだ日本中にたくさんある。こうしたものをもっと掘り起こし、すでにあるもの同士、あるいはAIなどの先端技術と掛けあわせることで、さらに新しいコンテンツを生み出すこともできるでしょう」(花沢氏)
一方で、「日本にはこうしたアドバンテージがあるものの、教育と繋がっていない」と花沢氏は指摘。「世界から一目置かれているものの実践者・経験者・研究者と子供たちをいかにつなげていくかが日本の学校の大きな役割。これは世界で活躍する人材を育成するうえで、非常に重要な鍵になる。日本の教育者は、このような世界でユニークなコンテンツを生かした学びを実現できるということをメリットに感じてほしい」と強調した。
国際化=「世界に出ていく」ではない
4つ目は、必ずしも国際化のために「世界に出ていく」必要はないということだ。
「もはや、『日本vs世界』と対峙させる発想そのものが古い。デジタルネイティブ世代である若者たちは、国単位ではなく『世界はすぐ隣にある』という認識で生きている」と言い、「教育現場は子供たちに『もっと世界に出ていけ』と外に押し出すよりも、英語で日本のことを学べる環境を整え、世界からもっと人を呼び込むことからスタートすれば良いのではないか」と花沢氏は提起した。
「日本の魅力に惹かれ、『日本で学んでみたい』あるいは『わが子を日本で学ばせてみたい』と希望する海外の人々は少なくない」と花沢氏は言う。問題は今の日本に、海外からの子供たちを受け入れる土壌がないことだ。今回のセミナーには、止まらない少子化を見据えた経営を迫られる教育関係者も多く、特にこの場面では熱心に耳を傾けているようすが見られた。
探究学習を世界で勝負するチャンスに
花沢氏は、日本で始まった探究学習についても、「先生自身に知識や経験がなくても、身近にあるものの魅力を、それをよく知る地元の人々を総動員して進め、最終的に英語で発表する。英語で発表するのも、今はテクノロジーを使えば簡単にできる。そうやって、世界に出ていかなくても、日本から世界で勝負するチャンスはいくらでもある」と言い、「探究学習をきっかけに日本全国の教育を変えていける」と鼓舞した。
出席者からは、「日本の歴史と伝統、自然と風土の豊かさは世界に通用すると感じた。日本の強みの『掛け算』は大事な視点だと思った」「将来に悲観的にならず、生徒の未来を明るく拓いてゆく日本の潜在力を感じた」「不確実な未来を生きる子供たちにヒントを与えられるお話だった」といった感想が数多く寄せられ、懇親会では花沢氏と参加者が懇談するなど、実りの秋にふさわしいセミナーとなった。

地域の資源と人材を総動員して生徒と世界へつなげていく
「日本はすでに世界の中にある」―認識があらたまる、示唆に富む講演だった。確かにコロナ禍が明けて以降、全国で外国人観光客を多く見るようになった。インバウンド増加の背景には、もちろん円安や、ビザ免除措置など政策の影響も大きいだろうが、花沢氏の言うとおり、全国各地に世界に誇れるコンテンツが眠っているからなのだろう。
世界で活躍する日本人を育てるためには、がむしゃらに「海外をみて、出て行くこと」だけを目指す時代ではない。まずは地元の資源や人材に目を向け、コンテンツおよびそれを知る人と生徒をつなげて、英語で発信していくこと。そうした取組みがどこかの誰かの目にとどまるチャンスにもなり、また、生徒の土台を作ることにもつながるのではないだろうか。