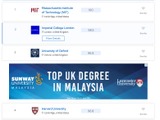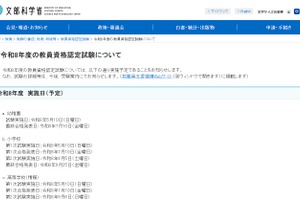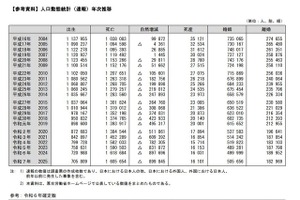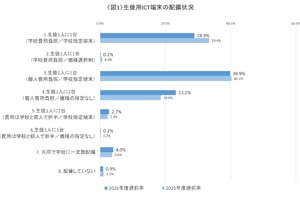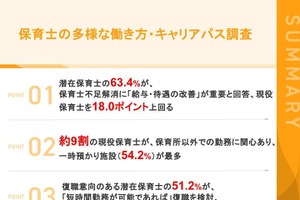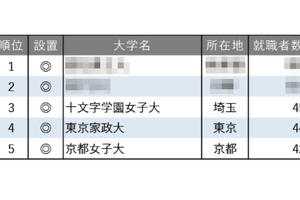文部科学省は2025年4月22日、大学研究力強化に向けた課題分析に関する2024年度の調査結果を公表した。「学術的貢献」「次世代人材への貢献」「社会的貢献」の3つの観点から研究力を測る指標(KGI)を整理している。
文部科学省は、大学ファンドによる国際卓越研究大学と、地域中核・特色ある研究大学がともに発展し、日本全体の研究力の発展を牽引することを目指し政策を実行している。大学の研究力強化に向けた課題分析に関する調査業務では、研究力強化に必要な要素を整理・モデル化し、大学の改革・取組みを後押しする。
調査対象は、THE、QSランキングなどで研究力が高く評価されている国内外の大学が中心。地域、規模、設置形態による偏りがないよう調査を行い、国内大学は、国際卓越研究大学への申請大学を中心に、国立・私立大学を調査した。
ロジックモデル事例は、さまざまな属性の研究大学およびマックスプランク研究所を対象に、重視している要素や取組み、研究力を評価する指標との関連を整理。現状の研究力を測るために意識しているKGI(研究力のKGI)や、特に重視している要素が、研究力強化にどのように好影響を与えているのか(アウトカム)などを紹介している。
たとえば、カリフォルニア工科大学は、教員数約300人と小規模ながら研究レベルが非常に高いことが特色。事業・財務戦略とガバナンス体制を土台に、「研究人材の活躍」を特に重視している。「研究力のKGI」は、世界的に権威ある賞の受賞、全米アカデミーの会員、輩出した研究人材の活躍の3つ。戦略に対する納得の信頼、実行フェースにおける機動的なサポートによって、個々の教員のアクティビティを活性化していることが、アウトカム(研究力強化)に影響を与えているという。
また、大学ごとのロジックモデルの特色を反映したKPIの設定イメージとしてイリノイ大学を紹介。同大は、ロジックモデルにおいて「研究人材の活躍」を特に重視しており、指標には「Associate ProfessorからFull Professorへの昇進に費やす期間(Associate Professor在籍期間)」を設定し、研究者のプロダクティビティを計測し、改善に向けたアクションにつなげているという。
最終的な成果である「研究力」を測定する難しさは、成果が出るまでの時間軸の長さや、分野による違い、測定コストの問題などさまざま。ロジックモデルの評価・改善のためにも、「研究力」を測定・評価することは重要であり、その成果を明らかにすることは大学の存在理由を学内外に示し、理解や協力を得られる環境づくりにもつながるとしている。
同調査業務の結果は、文部科学省Webサイトで公開している。