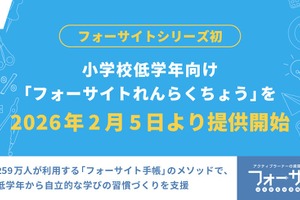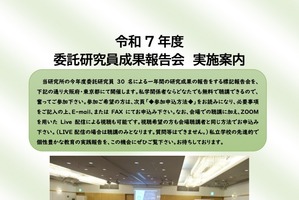学校に寄せられるさまざまな相談やクレーム。保護者や地域からの相談に先生はどのように対応するのが良いだろうか?クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第213回のテーマは「子供が教室に入れないので別室登校させてほしい」。
新型コロナの流行で学びのスタイルが多様に
子供が学校に行きたくない、教室に入れないということは昔から多くの人が悩んできたものです。各学校、自治体などがさまざまな工夫をしながら、その時の子供の学びを保障する取組みをしてきました。うまくいっている学校や自治体もあるのですが、なかなかうまくいっていないところがあるのも事実です。
そういった状況において、大きな変化を与えたものが新型コロナウイルス(コロナ)です。コロナによって、2020年春の一時期にすべての子供が学校に通うことができなくなりました。その後、さまざまな制限のある中、子供の学びを続ける工夫がされました。Zoomを用いたオンライン授業はそういったものの代表的なものです。そういったことが行われるようになったことで、それまで色々な事情で学校(教室)に行くことができなかった子供が授業に参加できるようになったという事例もありました。その後、Zoomなどを用いたオンライン授業は徐々に減る傾向にあります。私はそういったものは、すべて無くさずに、色々と難しさを抱える子供の学びを支えるツールとして残していって良いのではと思っています。
学校以外の学びも視野に入れ、子供を中心に考える
学校では、教室での学びに居心地の悪さを感じ、違う形で学んでいこうとしている子供が一定数います。以前は「登校拒否」と言われ、現在は「不登校」と言われています。先ほど紹介したように、オンラインを活用し、クラスでの学びを上手に繋げているケースもあります。ただ、それらは少数でしょう。
実際、学校に登校するけれども教室に入れないようなケースでは、別室が用意されることが多いです。部屋としては、保健室、カウンセリングルーム(相談室)、特別教室、図書室などが多いようです。学校の構造や別室を必要とする子供の人数などによって状況は違ってきます。
コロナの流行以降、学校以外の学びも多様になっています。通信制の高校、サポート校、自治体などが設定しているサポート教室などがあります。オンラインでの学びもとても充実してきています。世の中の仕事の中にはオンラインだけで完結するものもあります。そういった状況においては、学びもオンラインを中心にやっていった方が良い場合もあります。私が現在関わっている大学での教育もコロナ以降、オンラインでの学び(通信制)が充実してきています。
従来、学校はさまざまなトラブルを抱える子供や家庭に対して、学校以外の選択肢を勧めることに消極的でした。学校以外の選択肢を子供(保護者)が選ぶことは、学校にとって「敗北」のように捉えている面があったのだと思います。そういった考え方は間違っているのだと思います。不登校の子供にとって、学校に登校することが良いケースもあれば、違う選択肢を選んだ方が良いケースもあります。それぞれの状況によって、良いものは違ってきます。教員や保護者は、つい大人(自分)中心で物事を考えがちです。子供を中心に考えれば、自ずとすべきことが見えてくるでしょう。
本企画では、読者の皆さまからの質問を受け付けています。下記のボタンをクリックして表示されるフォームより送信ください。実際に学校へ寄せられた相談のほか、保護者が学校へ伝えた相談など、鈴木先生に対応方法を聞いてみたい相談事例を募集します。
質問をする