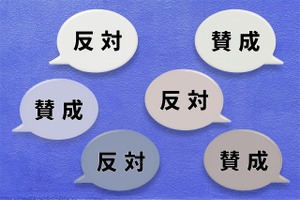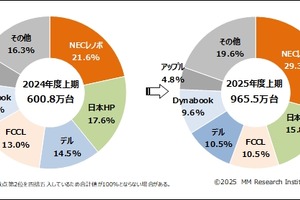学校に寄せられるさまざまな相談やクレーム。保護者や地域からの相談に先生はどのように対応するのが良いだろうか?クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第229回のテーマは「学校の安全性を高めてほしい」。
学校の安全は、ハードとソフトで対応
立川市の小学校で学校に侵入した人が教員を怪我させるという事件がありました。事件の詳細が少しずつ見えてきています。この事件は決して特別なものではないのでしょう。こういったことは、日本中のどこの学校でもあり得ることだと考えた方が良いのだと思います。
「子供が学ぶ場を安全なものにしてほしい」という願いは、保護者の誰もが思っていることでしょう。今回のようなショッキングな出来事があるとさらにそういった思いは強くなります。学校の置かれた環境によってセキュリティに関する状況は大きく違いがあります。学校に自由に出入りできるような所もありますし、門がオートロックになっている学校もあります。学校の状況は色々と違いがありますが、学校が取ることのできる対応策としては「ハード」と「ソフト」に分かれてきます。
ハード面の対応
「ハード」の対応としては、オートロックを設置することや刺股(さすまた)などの用具を準備することになります。ただオートロックに関しては少し難しい問題があります。設置することは予算さえあれば大丈夫なのですが、設置した後には「対応する人」が必要になります。多くの学校では、職員室内の副校長・教頭がいる場所のそばに対応するための機器が置かれているようです。オートロックは、解除に関わる対応が必要になり、その部分での難しさがあります。1日に100回の対応の必要がある学校では、その対応に1回30秒がかかったとすると、1日でオートロックの対応だけで50分が使われることとなります。他の仕事をしている最中に中断されることも仕事の質に影響を与えます。そういったこともあり、オートロックが設置されているけれども、それが運用されていないというケースもあるようです。
また、防犯グッズとして刺股を用意している学校もありますが、そこにも難しさがあります。実際に刺股で不審者を制圧しようとすると、かなりのテクニックが必要となります。そういったことを考えると、学校に常備する防犯グッズとしては、催涙スプレーやネットランチャー(網が飛び出してくるもの)の方が良いのかもしれないです。どちらの道具も使用に関して刺股ほど難易度は高くありません。
ハードを整えても、不審者が強い悪意を持って侵入を試みている状況であれば、学校へ侵入を防ぐことは難しいです。一般的に学校の外周は壁やフェンスなどで囲われています。乗り越えようとすれば、できないものではありません。門にオートロックがあった方が良いのですが、それだけで万全というものではありません。
ソフト面の対応
「ソフト」に関しては、職員の対応スキルを上げることや不審者などの情報が集まる仕組みを作ることなどです。私は小学校に勤めていた時、地元の警察署の方の協力のもと「本気の不審者対応訓練」というものをやったことがあります。子供が下校した後、不審者役を警察の方にしてもらっての訓練です。警察の方は「自分は全力で不審者を演じるので、先生達も本気で捕まえようとしてください」と言われて取り組みました。私たち教員は刺股などを持って本気で立ち向かったのですが、ほとんど歯が立ちませんでした。結局、本番なら数人が亡くなってしまうような状況でした。
大阪教育大学附属池田小学校では、そういった部分を強く意識した訓練に継続して取り組んでいます。そのようすを外部の人にも公開をしています。動画などもアップがされています。そういったものを見ることはとても勉強になります。
本企画では、読者の皆さまからの質問を受け付けています。下記のボタンをクリックして表示されるフォームより送信ください。実際に学校へ寄せられた相談のほか、保護者が学校へ伝えた相談など、鈴木先生に対応方法を聞いてみたい相談事例を募集します。
質問をする