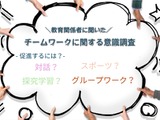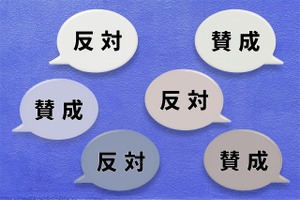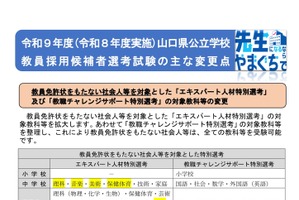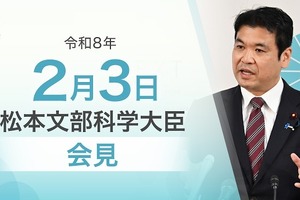学校に寄せられるさまざまな相談やクレーム。保護者や地域からのクレームに先生はどのように対応するのが良いだろうか?クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第240回のテーマは「夏休みに補習をしてほしい」。
補習の考え方は学校種によって異なる
夏休みに学校で補習を実施するというものは、学校種によって少し捉え方が違ってきます。高校の場合、大学受験に向けての補習ということになります。「0限」として朝に補習があり、夕方に「7限・8限」としてさらに補習を行なっている高校もあります。地方などで予備校などがあまりないエリアでは学校がそういった役割を担っている場合があります。
小学校の場合は、「サマースクール」などの名称で、勉強を教えるような取組みがあります。これは学校に保育所的機能をどれだけ持たせるのかという問題と関係してきます。小学校において保育所的機能をどれだけ持たせるのかということは、保護者の就労と関係があります。「小1の壁」と言われるもので、小学校入学によって子供を預かってもらえる時間が短くなり、保護者が大変になるというものです。昨今、働く人が増えています。学校がどの程度、保育所的機能を持つのかは、地域によっても違うでしょう。議会などにおいて議論し、どういった形が望ましいのかを探っていくと良いでしょう。
補習を実施する際に気を付けたいこと
このことは、学校(教員)の「定額働かせ放題」と関わってくると私は考えています。給特法における教職調整額の割合が4%でも10%でも本質は変わらないことです。民間の営利企業の場合、何か新しい取組みを行う際、その取組みを行うにあたって必要なコスト、人員などを計算します。そのうえで、その取組みによって得ることができるもの(売上)との兼ね合いにおいて、実施するか否かの判断をします。実施する際には、新たな人員を確保したり、それまで取り組んでいた活動の一部を中止したりするなどの対応を取ります。そういった流れの中で新たな取組みが行われていきます。
その点、学校は新たな取組みが行われることになっても、基本的には、新たなコストは発生しません。先ほど書いたように給特法による「定額働かせ放題」だからです。今回のテーマである夏休みの補習なども、学校で新たに取り組んだとしても、特にコスト的には問題はありません。各学校の工夫において取り組むというような感じになっていきます。
私は、現状のまま、夏休みの補習を学校(教員)が担っていくことには反対の立場です。教員と少数の職員(事務など)で取り組むにはかなりの無理があります。きちんと予算化して、現在の人員以外の人を確保する形であれば良いと思います。こういったテーマに関しては、東京都杉並区立和田中学校の好例があります。夏休みの補習だけでなく、週末や夜に、地域の人や学生などの協力によって子供の学びの場を新たに作りました。非常に参考になる取組みです。
さらに、最近、私が気になっていることに、学校の問題を考える際、人によって、考える前提条件が違っているということがあります。同じ言葉を使っていても、その言葉の捉え方が違っているのです。その結果、話をしていても、噛み合わないことになります。色々な話し合いをする際には、前提条件を確認し、その場の人の意識や言葉の理解を揃えることが必要でしょう。そのうえで、「ゼロベース」で考えていくことや外部の人の意見を聞くことが必要なのだと思います。
本企画では、読者の皆さまからの質問を受け付けています。下記のボタンをクリックして表示されるフォームより送信ください。実際に学校へ寄せられた相談のほか、保護者が学校へ伝えた相談など、鈴木先生に対応方法を聞いてみたい相談事例を募集します。
質問をする