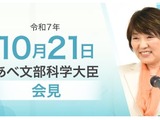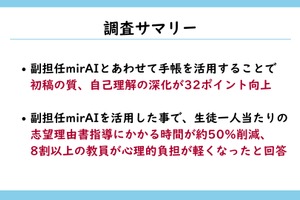学校に寄せられるさまざまな相談やクレーム。保護者や地域からの相談に先生はどのように対応するのが良いだろうか?クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第252回のテーマは「学校行事を減らさないでほしい」。
学校行事はコンパクトな形に
新型コロナウイルスによって学校行事は量も質も大きな変化がありました。運動会の午前中のみの開催、保護者会のオンラインでの実施などです。そういったことに関して、賛成する立場の人、反対する立場の人、どちらもいると思います。
私は、学校行事はコンパクトな形にしていくのが良いと思っています。理由としては、学校の現状を見ると明らかに余裕の無い学校が多いからです。学校のことを「パンパンに空気の入った風船のようだ」と例えられることがあります。そういった状況では、小さな刺激で割れてしまいます。「子供の不登校」「教員の休職者の増加」などがそういったものにあたるのでしょう。
学校が取り組むさまざまなものの中には、学校がコントロールできるものとできないものがあります。たとえば、文部科学省が定めている「学習指導要領」はそれぞれの学校が変えて取り組んで良いものではありません。また、学校のある自治体の教育委員会が定めたもの(夏休みの期間など)も同様に学校がそれぞれの判断で変えられるものではありません。
上記のように文部科学省や教育委員会で決められているものもあるのですが、学校の判断で決められるものも意外とたくさんあります。それぞれの学校の「教育課程」については学校長に権限があります。また、今回のテーマである「学校行事」などについても、その実施の有無や取り組む際の内容などについては各学校で決めることができる内容です。そういった各学校で決めることができる部分において、それぞれの学校の特色を出しながら、学校がスリムになるようにしていくことが望まれます。
先ほども書きましたが、私は基本的には学校行事は減らしていくべきだと思っています。これまで色々なものを増やし続けてきた結果が現在の学校の姿です。学校という組織では、増やすことは簡単なのですが、減らすことはとても難しいです。「子供のために・・・」という言葉によって多くのことが取り組まれるようになってきました。「子供のためになるから新たに〇〇教育に取り組みたいのですが・・・」という意見は職員会議などで受け入れやすいです。確かにそのことだけを見れば子供の育ちにつながるのかもしれません。ただ全体を見ると、子供も教師も余裕がなくなり、取組みは中途半端になり、場合によっては大きなトラブルが発生するようなことにもなりかねません。
学校も時代に合った形へ
勇気を持って「次年度は〇〇は無くす方向でいきましょう」と言う人がいる学校は良い方向へ変わっていく可能性があります。特に学校長がそういった役割をすると非常にスムーズに進んでいきます。行事などを減らしていくのですが、学校として力を入れていきたいところは増やすということも大事です。何でも減らせば良い訳ではありません。その学校で力を入れたい部分(特色)はしっかりと残し、場合によってはより取り組む時間を増やすようにしていきたいです。社会の変化は激しいです。学校も時代に合った形に変わっていくことが大切なのでしょう。
本企画では、読者の皆さまからの質問を受け付けています。下記のボタンをクリックして表示されるフォームより送信ください。実際に学校へ寄せられた相談のほか、保護者が学校へ伝えた相談など、鈴木先生に対応方法を聞いてみたい相談事例を募集します。
質問をする