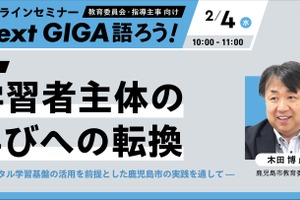学校に寄せられるさまざまな相談やクレーム。保護者や地域からの相談に先生はどのように対応するのが良いだろうか?クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第205回のテーマは「担任から怒鳴られ、トラウマになり学校に行かれない」。
不登校の原因から見えてくるもの
まず、不登校などの現状から確認します。最近、栃木県が子供の欠席に関する調査を行いました。学校を休むきっかけとしてもっとも高かったものは学校種別で次のようになっています。
小学生「先生との関係」45.8%
中学生「学校やクラスの雰囲気」42.5%
高校生「体の不調」41.7%
小学生の「先生」はもちろん、中学生の「学校やクラスの雰囲気」には教員も大きく関わっています。子供の学校での生活の質に、教員が影響を与えていることがこういった調査でもよくわかります。
日々の学校での生活では、教員が子供を指導する場面が発生します。そのやり方をきちんと考えていくことが大切になります。学校の教員は学校教育法第11条で「懲戒」が認められています。どういった場合が「懲戒」にあたり、どういった場合が「体罰」になるのかということも文科省が示しています。たとえば、「立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせること」「当番を多く割り当てること」「部活の練習に遅刻した生徒を試合に出さず見学をさせること」「授業中、教室内に起立させること」などが「懲戒」にあたると示されています。
教員の影響力は大きい
私は長く小学校の教員をしてきました。その中で「きちんとしている」クラスというものをいくつも見てきました。朝会・集会などでの態度も良く、挨拶もよくできているなどです。問題は、どういったやり方でその状況になっているかということです。教員の適切な関わり(個に応じて、温かく、細やかなもの)によって、そういった状況ができているのであればとても良いことです。
しかし、そのきちんとした状態が、教員の「厳しい指導」などによって成り立っているのであれば、それは話が違ってきます。そういったものと関連するものに「ダークペタゴジー(闇の教授法)」というものがあります。「恐怖の条件付け」とも言い、人を恐怖によって従わせるというものです。教員が、恐怖、威圧、大声などを用いて、学級を動かしていくというやり方です。そういった状況では、脳の恐怖中枢を刺激します。密室的環境において、他者をコントロールする時に行われることが多いとされています。小学校の学級のほか、中学校の部活、入院病棟、監獄、捕虜収容所などで起こり得るとされています。こういった状況でのきちんとしている状態は、子供の学びや育ちによるものではありません。その恐怖がなくなると、途端に状況が悪化します。強さを用いてコントロールしている学級で、他の専科の教員の授業の時には子供が乱れてしまうなどの状況がそういったものです。
強さのようなものを用いた指導は、子供の学びを阻害する可能性が高いです。そのうえ、今回のテーマにもあるように、それがトラウマのように残り、違う影響が出てしまうこともあります。具体的な形としては「学校に行けない」などです。子供に対する教員の影響力はとても大きなものです。教員はそういったことを常に考えて行動していきたいです。
本企画では、読者の皆さまからの質問を受け付けています。下記のボタンをクリックして表示されるフォームより送信ください。実際に学校へ寄せられた相談のほか、保護者が学校へ伝えた相談など、鈴木先生に対応方法を聞いてみたい相談事例を募集します。
質問をする