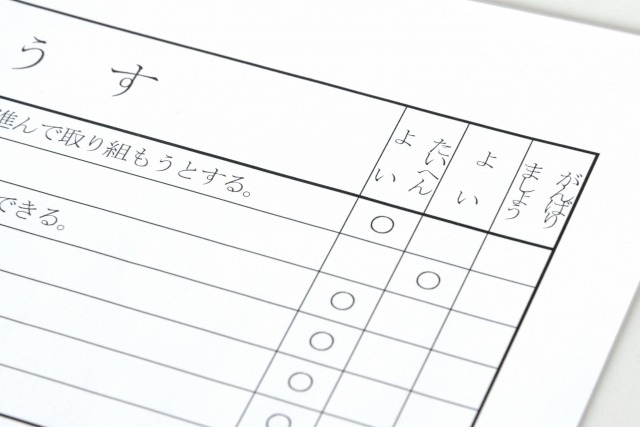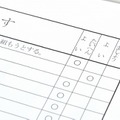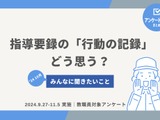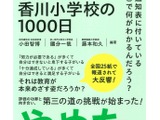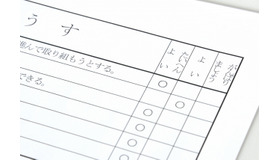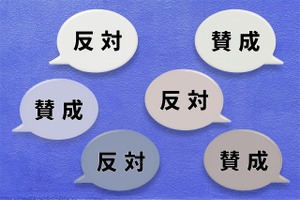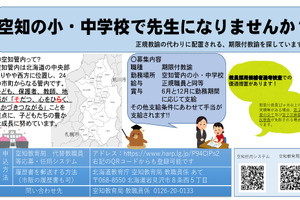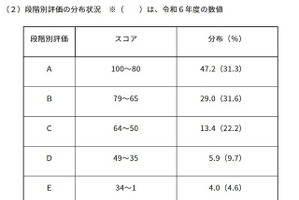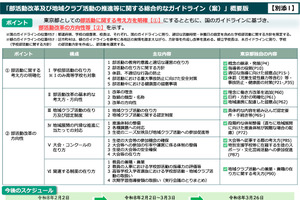学校に寄せられるさまざまな相談やクレーム。保護者や地域からの相談に先生はどのように対応するのが良いだろうか?クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第210回のテーマは「通知表がわかりにくい」。
通知表が保護者からの不満に繋がる可能性も
通知表の時期です。通知表は学校と保護者の間でわだかまりが生じやすい事柄です。保護者は疑問などを抱いても、成績に関することは、何となく学校に聞きにくい雰囲気があります。モヤモヤとした思いを抱えたままになりやすいです。学校としては、できる限りていねいな取組みをして、保護者が疑問や不信を抱くことにならないようにしていくことが大切です。
今回のテーマである「通知表がわかりにくい」ということは、先ほども書いたように保護者が学校(先生)に疑問や不信を抱くことに繋がりやすいです。わかりにくい要素はいくつかあるのですが、その1つが「言葉づかい」です。教員は学校の内部で使っている言葉をそのまま外部の人にも使ってしまうことがあります。たとえば、通知表のコメント欄です。その欄は、字数に制限があることもあり、字数を少なくするために漢字が多くなりがちです。その結果として、文章が少しわかりにくくなることがあります。
ある保護者から通知表に関して私は次のようなことを聞きました。小学校2年生の通知表のコメントに「曲想」という言葉が書かれていて、少しわかりにくかったそうです。「曲想」という言葉は、何となく雰囲気はわかりますが、はっきりとは捉えにくいものです。「曲想」という言葉は、学習指導要領に示されており、「その音楽に固有な雰囲気や表情、味わいのこと」と説明されています。教師にとってはある程度一般的であり、馴染みのある言葉です。しかし、通知表を受け取る親や子供にとると、その言葉は馴染みのあるものではないでしょう。字数は増えてしまいますが「曲の雰囲気」などの言葉を使っていれば、より多くの人に伝わりやすくなることでしょう。
上記の「曲想」の例ではありませんが、「わかりやすく伝えていく」ことは教員にとって非常に大切です。教員の話や説明は、一方的になりやすい面があります。ところで、色々な説明などをして、その後に「わかった?」と教員が聞き、その後に子供が「はーい」と手を挙げて答える場面をよく見かけます。ただ、このやり取りはあまり意味ないと私は感じています。教師が「わかった?」と聞くと、年齢にもよりますが、わかっていても、わかっていなくても、ほとんどの子供が「わかった!」と手を挙げてしまうことが多いからです。わかっていない子供を見つけ、わからない部分をわかるようにするという役目を果たしていないことが多いです。
この場合では、「何かわからないことはありますか?」という聞き方であれば、子供の行動が少し違ってきます。「あっ、この部分がわからないから聞いてみよう」という感じで、子供から質問が出てくることがあります。こういう配慮が色々な場面で必要でしょう。そういった視点で通知表を見ていくと、書きぶりも変わってくるはずです。学校(教員)と保護者のやり取り、特にその際の言葉の使い方には気を配りたいです。通知表はそういったやり取りの中でも、重要度の高いものです。通知表をきっかけにして親から不信感を抱かれたりすることのないように、ていねいな取組みが望まれます。
本企画では、読者の皆さまからの質問を受け付けています。下記のボタンをクリックして表示されるフォームより送信ください。実際に学校へ寄せられた相談のほか、保護者が学校へ伝えた相談など、鈴木先生に対応方法を聞いてみたい相談事例を募集します。
質問をする