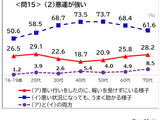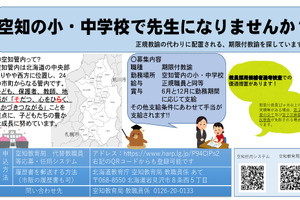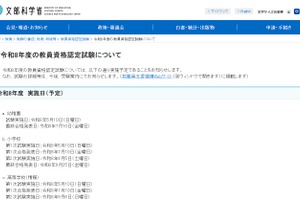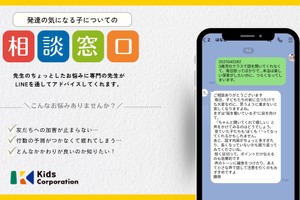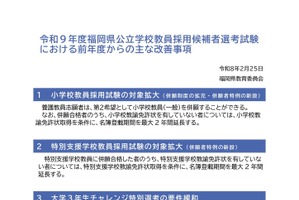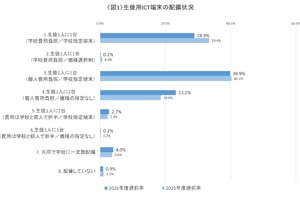ローマ字のつづり方について、文化審議会は2025年8月20日、現在広く使われている「ヘボン式」を基本とする表記に見直す答申をまとめ、文部科学省に提出した。ローマ字のつづり方の改定は、約70年ぶりとなる。
ローマ字のつづり方には、一般に「訓令式」「ヘボン式(標準式)」「日本式」と呼ばれるものがある。現行では、1954年の内閣告示「第1表」で示された「訓令式」が用いられてきたが、実際には「第2表」が掲げる「ヘボン式」がパスポートや道路標識など、多くの場面で採用されてきている。
たとえば、「訓令式」は「し」を「si」、「ち」を「ti」、「つ」を「tu」、「ふ」を「hu」とするが、「ヘボン式」では「し」を「shi」、「ち」を「chi」、「つ」を「tsu」、「ふ」を「fu」と表記している。
今回、ローマ字使用の現状を踏まえ、国語におけるローマ字が将来にわたって適切に用いられ、円滑な言語コミュニケーションに資するものとなるよう、ローマ字のつづりや表記の慣習を整理。これまでの審議を踏まえ、「改定ローマ字のつづり方」を取りまとめた。
「改定ローマ字のつづり方」では、社会で実際に用いられ、各種調査結果でも多くの人が慣れ親しんでいるヘボン式の「shi」「tsu」「chi」「fu」「ju」などを採用。長音で発音される語は、歴史的経緯と社会の実態を踏まえ、「kāsan(母さん)」「Tōhoku(東北)」など、これまでと同様に母音字に長音符号を付して表する。なお、符号については、「¯」の使用が定着するまで、必要な場合には現行内閣告示が示してきた「^」(サーカムフレックス)を用いても差し支えないとしている。
イ列と一部のエ列の長音は、符号を用いない慣用があることから、「niisan(兄さん)」「shiitake(しいたけ)」のように母音字を並べて書く。また、符号を付さない場合にも長音であることがわかるようにするため、「kaasan(母さん)」「Touhoku(東北)」など、母音字を並べる方法も導入する。
撥音(はねる音)、促音(つまる音)については、できるだけ複雑にならない考え方を採用。従来どおり、撥音は一律に「n」を用いて書き「anman(あんまん)」「kanpai(乾杯)」など、促音は一律に子音字を重ねて表す「teppan(鉄板)」「nicchoku(日直)」などとした。
一方、すでに定着している表記については、急に変更することになれば、混乱や予定外の経済的負担を生じる恐れがあることから、直ちに変更を求めない。個人の姓名、団体名などをローマ字で書き表す場合は、当事者の意思を尊重するよう配慮するとしている。