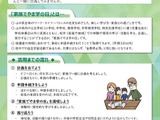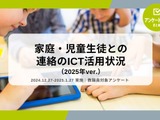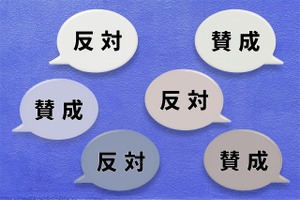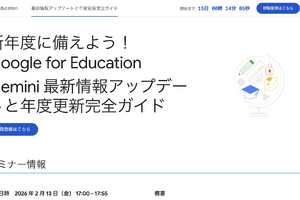学校に寄せられるさまざまな相談やクレーム。保護者や地域からの相談に先生はどのように対応するのが良いだろうか?クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第226回のテーマは「学校を休んで旅行に行きたい」。
ラーケーション制度を導入する自治体が増加
学校を休んで旅行などに行くことの是非は昔から話題となっていました。そういったことと関連して、現在は「ラーケーション」制度を導入する自治体も増えています。「ラーケーション」は、自治体によって少しずつ運用は違うのですが、子供が保護者などと共に平日に学校を休んで学びや体験活動に取り組むもので、学校の欠席日数を一定の条件で出席扱いとするというものです。都道府県レベルでは、愛知県(名古屋市をのぞく)、山口県、茨城県、熊本県が導入しています。また、市町村レベルでは、大分県別府市、沖縄県座間味村、栃木県日光市、静岡県磐田市、滋賀県長浜市などが実施しています。
2025年の5月の連休の場合、4月28日(月)、4月30日(水)、5月1日(木)、5月2日(金)を休みとすると、4月26日(土)から5月6日(火・祝)までの11日間の休みになります。こういった日程のことやニュースなどでラーケーションが話題になっていることもあり、「学校を休んで旅行に行きたい」や「休んだ場合、ラーケーションとして認められないのか?」などの申し出があるかもしれません。この件に関しては、自治体としてルールに定められていない場合は、通常の欠席として扱われるでしょう。
ところで、ラーケーションが話題になっていること、皆勤賞の是非が話題になっていることは、新型コロナウイルスの流行が関係していると私は考えています。それは、「学校に行くこと」の意味が曖昧になったからです。たとえば、2020年から2021年にかけて、「少しでも体調が悪い時(発熱など)は学校に登校しない」ことが求められました。また、感染が不安な場合、登校しない選択肢がありました。Zoomなどを用いて、学びの手段も多様になっています。
コロナ以前は「出席」と「欠席」の間に厳密な違い(差)ありました。それが、コロナへの感染を防ぐということで曖昧な状況になっていました。感染を抑えるという点では、良かったのだと思います。そういったことによって、学校に行くということはどういうことなのか、学校外の学びもあるのではないか、毎日学校に行くことが表彰されることなのかなどを親も子供も教員も考えることとなりました。
学校へ通うことの意味・意義を考える
学校へ通うことの意味・意義を子供も、親も、教員も考える機会ができたことは良いことだったと私は思っています。子供も、親も、教員も、それぞれの立場でそれまではあまり考えずに済ませていたものを考えることとなっています。何となく子供が学校に通うのではなく、何のために通うのかということをそれぞれの立場で考えることで、日々の学校での教育活動の質の高まりが期待できます。
また、学校へ通うことの意味・意義を考えることは、「学校へ通わない」という選択についても考えることになります。コロナを経て、高校や大学では通信制の学びが充実しました。現在、日本でもっとも生徒数の多い高校は通信制のN高・S高などです。積極的に通信制の学びを選ぶ人が増えています。義務教育段階では、フリースクールや学びの多様化学校も増えてきています。ホームスクールという仕組みもあります。
コロナを経て、学びの選択肢が一気に増えてきました。学校に「普通」に通うことだけが子供の学びではありません。広い視野で子供の学びというものを考えていきたいです。
本企画では、読者の皆さまからの質問を受け付けています。下記のボタンをクリックして表示されるフォームより送信ください。実際に学校へ寄せられた相談のほか、保護者が学校へ伝えた相談など、鈴木先生に対応方法を聞いてみたい相談事例を募集します。
質問をする