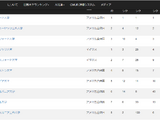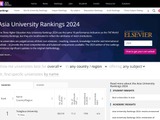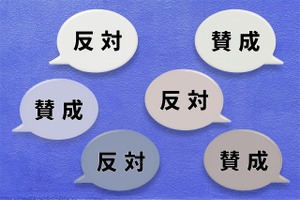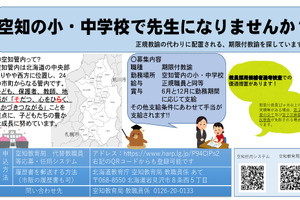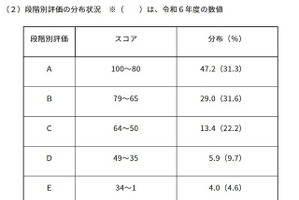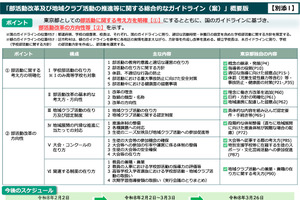学校に寄せられるさまざまな相談やクレーム。保護者や地域からの相談に先生はどのように対応するのが良いだろうか?クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第180回のテーマは「家庭学習(宿題)のやり方がわからない」。
宿題の取り組み方に変化
子供の学びと関連して「個別最適な学び」や「自由進度学習」などの言葉をよく聞くようになりました。それぞれの子供の特性に応じた学びに取り組み、より良い育ちにつなげていこうというものです。そういった個に応じた学びと関連し、家庭学習(宿題など)の取り組み方が変化してきている部分があります。今回のテーマは「家庭学習のやり方がわからない」です。
これまで、学校における「宿題」の取り組み方は、すべての子供が同じものに取り組むということが多かったです。その日に取り組んだ内容について、さらに理解を深めるような内容です。たとえば、「その日に新たに学んだ漢字について、何度か書く練習をし、その漢字を使った文章を考えて、それをノートに書く」「その日の取り組んだ掛け算の九九を家で何度も練習し、すらすらと言うことができるようにする」などのものです。
例にあげた漢字練習や九九のような宿題であれば、やり方に困ることはほとんどないはずです。しかし、個に応じた学びと関連し、先ほども書いたように宿題に取り組み方が変わり出してきている部分もあります。そういったことで親も苦労しているケースがあります。
新型コロナウイルスの流行前から取り組まれていた宿題のやり方に「自主学習」があります。それぞれが自分で学ぶテーマや内容を決めて取り組むというものです。私が小学校の担任をしていたころ、昆虫が大好きな子供が自主学習の宿題で色々な昆虫について詳しく調べていました。他には、縄跳びに取り組んだり、小説を書いたり、絵を描いたりと、それぞれの子供が自分の良さを伸ばすために取り組んでいました。
個に応じた学びは、周りの大人が適切に関わることが重要
ただ難しいのが、こういった個に応じた学びは教師や親が丁寧に関わらないと質の高い学びとはならないケースがあることです。最近、学校で行われている「自由進度学習」も同様です。子供に一人で学ぶ力が一定程度あることで成り立つものでしょう。何でも子供に任せる(丸投げ)だけでは良い学びとはなりません。学び方をしっかりと学ぶことで、質の高い学びとすることができます。逆に、学び方などをきちんと取り組まず、形だけ「自主学習」「自由進度学習」などに取り組んでも、一斉授業のような取組みよりも質が下がってしまうことがよくあります。
新型コロナウイルスの流行以降、GIGA端末が身近にある環境となりました。GIGA端末は個別最適な学びとの相性がとても良いです。その子供の理解できているところ、できていないところの判別がとてもしやすくなりました。アプリなども急速にその質を高めてきています。ただ、先ほど書いたことと同様に、教師が適切に関わることなく、子供任せな感じではうまくいかないケースも出てきます。GIGA端末を使うことで、子供の状況の把握がしやすくなりました。そういった情報を上手に活用することで、日々の学習の質も高まりますし、家庭学習(宿題)の質も高めていくことができます。個々の「学びの質」ということを意識した取組みがこれまで以上に行われていくと良いでしょう。
本企画では、読者の皆さまからの質問を受け付けています。下記のボタンをクリックして表示されるフォームより送信ください。実際に学校へ寄せられた相談のほか、保護者が学校へ伝えた相談など、鈴木先生に対応方法を聞いてみたい相談事例を募集します。
質問をする