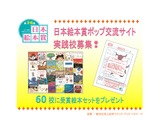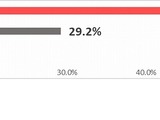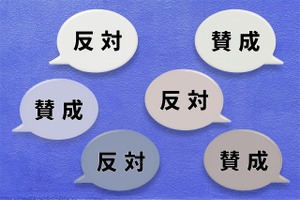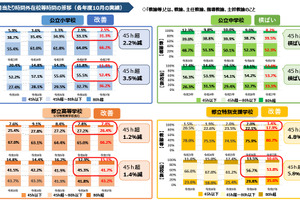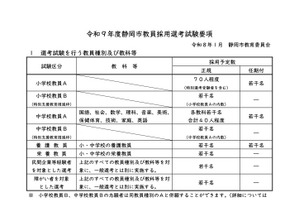コロナ禍で図書館が閉鎖、
本が読めない
新型コロナウイルスは暮らしのさまざまな面に影響を与えています。今回のテーマである「読書」に関しても影響がありました。地域や学校の「図書館(室)」が閉まってしまったことです。今回は、コロナ禍における子供と読書について書いていきたいと思います。
新型コロナウイルスの流行によって、一時的に学校の図書室を使用禁止にしたというケースがありました。また、街中にある公立の図書館も臨時閉館を余儀なくされたところがありました。図書館(室)という仕組み上、不特定の人が本等を触るということや多くの人が集まること等が不安視されてのことです。記事を書いている2021年7月時点では、さまざまな工夫によって、図書館を含めた公的な施設はサービスを行っているところが多いようです。
これまで書いてきたことと関連し、保護者から学校に「利用できなくなっている学校の図書室を早く使えるようにしてほしい」という意見が来ることが考えられます。本を読むことは学力を高めることと関連があります。どの教科でも文章理解力や表現力が学びに関連してきます。「朝読書」や「読み聞かせ」等を定期的に取り組んでいる学校が多いことはそういったことと関係があります。
「図書室を早く使わせてほしい」という意見に関しては、学校の状況によって対応が違ってきます。学校内で、大規模なクラスターが発生しているような状況でなくとも、どこかのクラスで新規感染者が発生しているような状況においては、図書室等を閉める必要が出てくるでしょう。人と人が接触する機会を減らすことが、感染予防の基本だからです。
電子書籍を活用しよう
こういった状況において子供や保護者に勧めていきたいものが「電子書籍」です。GIGAスクール構想の実現により、現在は日本中のほとんどの子供がPC/タブレットを一人一台で保有しています。まだ家庭への持ち帰り等が実施されていない自治体や学校もありますが、今後の方向性としては、家庭へ持ち帰るという形になっていきます。
PC/タブレットを積極的に活用していくことで、コロナ禍における読書量が落ちてしまうという問題にある程度対応することができます。数年後には教科書もデジタル化され、PC/タブレットの中に入るようになるとされています。そうなってくると、現在は手に取って読んでいる書籍も、電子化されるものが増えてきます。
現在、公立の図書館でも、電子書籍の貸し出しを行っている所があります。また、毎月一定額を支払うことで、書籍が読み放題になるサービスがいくつもあります。そういったサービスでは、利用者が増えるにつれて、本のラインアップが大人を対象としたものだけでなく、子供が楽しめるものも増えてきています。そういったサービスを効果的に活用することで、コロナ禍における本離れの問題にある程度対応ができそうです。
ただ、読書だけではないのですが、目の健康等への配慮は忘れないようにしたいです。紙の書籍を読むことと比べ、タブレット等で電子書籍を読むことは、目に負担がかかります。そういったことを伝えていくことも大切です。
本企画では、読者の皆さまからの質問を受け付けています。下記のボタンをクリックして表示されるフォームより送信ください。
質問をする