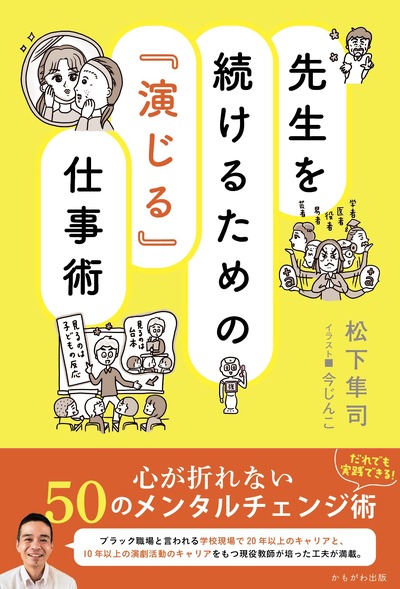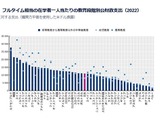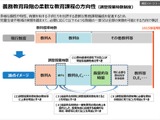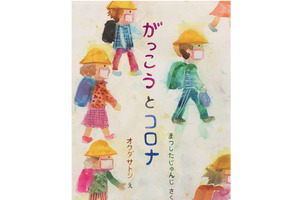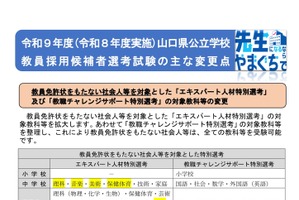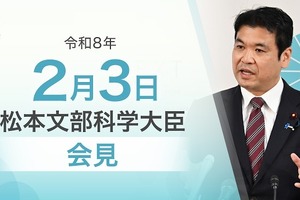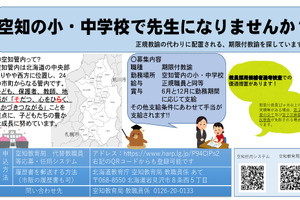教育現場で日々奮闘されている先生へ。リシードは、現役の小学校教諭である松下隼司氏による連載「先生の事情とホンネ」を毎月掲載している。
文部科学大臣優秀教職員表彰を受賞した経験をもち、教育書の執筆も手掛ける松下教諭が、日々どのようなことを考えて子供たちと向き合っているのか。授業や教室運営の工夫を紹介するほか、未来を担う子供たちの教育に携わる「教員」という仕事の魅力も発信していく。
第7回のテーマは「20年前の学校のほうが、しんどかったこと」。過酷だった20年前の教育環境を振り返り、「今の教育環境がしんどい…」と感じている先生に向けて、心がスッと軽くなるような話題を紹介する。
20年前の学校のほうが、しんどかったこと
年々、テレビや新聞、SNSなどで、「教師の労働環境のしんどさ」と「子供の教育環境のしんどさ」をとてもよく目にするようになりました。
確かに…と納得する情報ばかりですが、“令和の学校”にはないしんどさが20年ほど前の“平成の学校”にはありました。今、思い返せば、「よくあんな過酷な環境で子供たちも先生たちもがんばっていたな~」と思います。そして、「今はありがたい教育環境だな~」と思います。今の教育環境がしんどく思われている方の気持ちが、スッと軽くなる20年前の過酷な教育環境を紹介いたします。
エアコンどころか、扇風機も教室になかった
私が教師になった2003年から10年間ほどは、教室にエアコンはもちろん、扇風機もありませんでした。


令和の夏はエアコンなしでは危険なほどの暑さですが、平成の夏も十分に暑かったです。7月~9月の教室の気温は、30人以上の子供たちの体温も相まってゆうに30度を超えます。湿度も汗ばむ子供たちの影響で高かったです。
(1) 下敷きをうちわ代わりにして仰いでいた
今は、湿度、日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、 気温の3つ要素を組み合わせて算出した暑さ指数(WBGT)が31以上になると「危険」となるため、屋外での運動は避けるように言われています。
しかし、20年前はそのような基準がありませんでした。だから、真夏でも休み時間は運動場で子供たちは遊んでいました。そして、休み時間が終わって、エアコンも扇風機もない教室に戻ってきた子どもたちは、真っ先に、下敷きをうちわ代わりに扇いでいました。「授業中に下敷きで仰ぐなんてマナーが悪いんじゃないか?」「授業規律がなっていないんじゃないか?」と思われるかもしれません。
私も最初はそう思っていましたが、子供と休み時間、一緒に運動場で遊んでわかりました。下敷きで仰がないと耐えられない…と。特に、9月初旬の体育の授業で運動会練習をした直後です。そこで、子供たちに
「今から、1分間、仰いでいいよ~」
と言うこともありました。
(2)授業中に、上半身裸になる子供がいた
エアコンが効いた今の教室は快適です。教室に入った瞬間、
「はぁ~~~涼しい」
と思わず言うほど心地よいです。癒されます。でも、エアコンも扇風機もなかった頃は、暑さでイライラする子供もいました(私もです)。
「あ~暑すぎる!!!」
と怒って、授業中に突然、Tシャツを脱いで上半身、裸になってしまう男の子もいました。
そこで、エアコンがついている図書室や多目的室に移動して授業していました。扇風機を自費で購入して教室に置いたこともありました。授業中に子どもたちに水の入った霧吹きをかけてあげることもありました。ミスト代わりです。また、自費で購入した冷却スプレーをかけてあげることもありました。とても喜んでいました。
(3)給食の残食が多かった
教室の気温がぐんと上がるのが、給食の時間です。米飯やお味噌汁などの湯気も加わって、教室はムンムンとします。給食の前の4時間目が体育の授業だと、体を動かした子供たちの体温と汗でさらに教室の気温が上がります。
暑い教室の中で、給食で熱い汁物系のおかずの日は、残食が多かったです(特に体育の直後)。食欲が湧かない子供がいました。その分、食べられる子供たちが頑張って食べていました(昔は、給食の残食に対しての捉え方もとても厳しかったです。給食室前で残食調べがありました)。
また、「いただきます」の挨拶をしたら、まず真っ先に牛乳を飲み干す子供が多かったです。今は、そうした子供たちの姿も見なくなりました。
冬は、ストーブ
エアコンが教室になかった頃は、冬になると教室にストーブを置いていました。ストーブの周りには柵があります。ストーブをつけるのは授業中だけで、休み時間は切るという決まりがあったのを覚えています。換気のためです(それとやんちゃな子供がストーブで手を温めるふりをして、ストーブの上に、小さくちぎった消しゴム、鉛筆の削りかす、髪の毛を置いて燃やすのを防ぐためです)。
ストーブだと教室全体はあたたかくなりません。だから、教室での授業も自分が吐く息は白かったです。
あまりに寒いので、ダウンジャケットを着て授業をしていました。子供たちも厚着をしていました。家から座布団を持って来て、椅子の上に置く子供も多かったです。そして、椅子とお尻の間に手を挟んで、指先をあたためる子供の姿をよく見ました。教室での授業中もポケットに手を入れる子供が多かったです。
「寒すぎて、字をちゃんと書けない」
という子供のつぶやきもよく聞きました。今はそういった子供の姿やつぶやきがとても少なくなりました。本当にありがたい環境です。
通知表や指導要録の所見を、手書き&ハンコ
パソコンで通知表や指導要録を作成するのが、今は当たり前になりました。でも、20代の頃は、手書きでした。評定はハンコを押していました。間違ったら、パソコンだと簡単に訂正できますが、手書きの頃は大変でした。普通の消しゴムでは消せないので、強力な消しゴムや電動消しゴムを購入して、削り取っていました。その手間を減らすために、鉛筆で下書きをしていました。

電動消しゴムや強力な消しゴムで、紙に穴が開いてしまったことがあります…。
もちろん手書きの良さもありますが、パソコンによって通知表や指導要録にかける時間がものすごく短くなりとても助かりました。私は字が美しくないので、その点でもありがたいです。
教科書を大きな模造紙に印刷していた
今は大型テレビが各教室に置いてあって、デジタル教科書を開いて、大きなモニターに提示することができます。
でも、教師になって15年間ほどは、そういったものがありませんでした。教室にあるテレビも薄型でなく、四角い形でした。画面も小さかったです。だから、教科書を模造紙に大きく印刷してそれを黒板に磁石で貼って授業していました。模造紙の印刷は、普通の印刷と違って時間がかかります。休み時間にあわてて印刷して、「早く印刷して~!」とイライラしながら待つこともありました。
そこで、自費で書画カメラや電子黒板とプロジェクターを購入して授業していました(書画カメラは教室に1台あればいいのですが、高価なので学年に1台の学校もありました)。
給食の牛乳は瓶だった
今は、学校給食の牛乳は「紙パック」の学校が増えています。でも、10年ほど前までは「瓶」※注でした。牛乳瓶には、紙パックにない心配事が多かったです。 ※注 地域によります
いちばんの心配は、割れることす。給食室から教室に当番の子供が運んでいるときに、うっかり牛乳瓶が入っているかごを落としてしまい、たくさんの牛乳瓶が割れてしまったことがあります。瓶が割れて、ガラスの破片の片づけは危ないので、子供にやらせないことが多かったです。牛乳の予備がない場合は、その日の給食の牛乳はなくなります…。今の紙パックタイプの牛乳は割れることがないので、本当に助かります。
また、倒れてこぼれてしまうことも牛乳瓶の心配でした。瓶は紙パックに比べると細長く不安定です。ふたを開けた机の上に置いた牛乳瓶がつい肘に当たって、倒れてしまいこぼれてしまうこともよく起きました。牛乳が大好きな子供の瓶が倒れてしまって、泣いてしまったり、喧嘩になってしまったりしたこともありました。
まだ蓋を開けていない牛乳瓶が床に落ちてしまったとき、割れなかったら
「ラッキー!」
と安堵する子供の姿をよく見かけました。私もほっとしました。子供たちが机のどこに牛乳瓶を置いているか確認していました。

今の紙パックタイプの牛乳は、瓶に比べて倒れにくいし、倒れてもこぼれる量は少ないです。割れる心配もなくなり、安全・安心です。
テレビや新聞やネットなどで見聞きする情報で、「昔に比べて今の学校教育はしんどい」というイメージが強いかもしれません。でも、年々、改善されていることもたくさんあります。子供にとっても、教員にとっても、過ごしやすくなっていることもあります。
連載「先生の事情とホンネ」