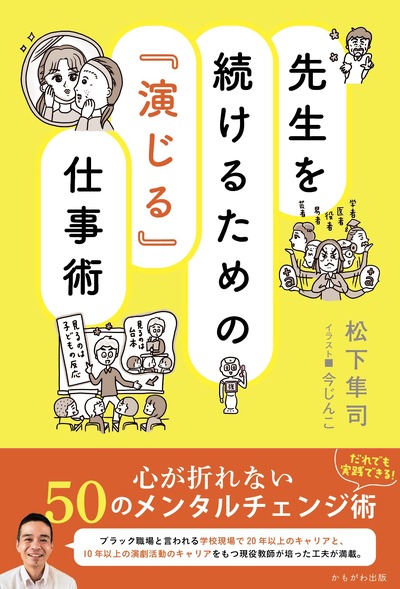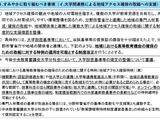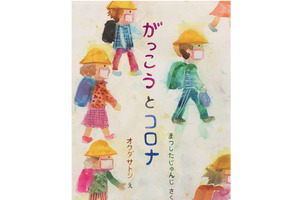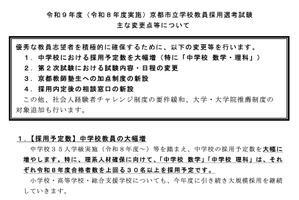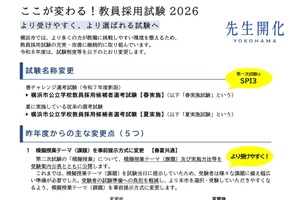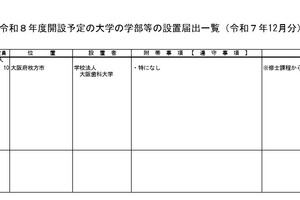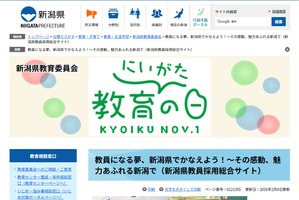教育現場で日々奮闘されている先生へ。リシードは、現役の小学校教諭である松下隼司氏による連載「先生の事情とホンネ」を毎月掲載している。
文部科学大臣優秀教職員表彰を受賞した経験をもち、教育書の執筆も手掛ける松下教諭が、日々どのようなことを考えて子供たちと向き合っているのか。授業や教室運営の工夫を紹介するほか、未来を担う子供たちの教育に携わる「教員」という仕事の魅力も発信していく。
第6回のテーマは「小学校教師にとっての『学校の謎ルール』」。小学校教諭歴23年の松下教諭が、これまでに不思議だと思った小学校の謎ルールについて解説する。
小学校教師にとっての「学校の謎ルール」
公立の小学校教師(23年目)の松下隼司と申します。保育園の年長の娘と、中学1年の息子の父親でもあります。
「学校の謎ルール」といえば、何を思い浮かべられるでしょうか。今は、だいぶ緩やかになってきましたが、たとえば次のようなルールのある学校もあります(担任の先生もいます)。
1) 真冬の運動場でも、体育の授業は半ズボン。寒くても上着を着てはいけない。
授業開始時は体があたたまっていないので、上着を着せてあげても良いと思います。
2) 給食で、苦手な食べ物を減らしたら、好きな食べ物のおかわりができない。
楽しいはずの給食の時間が苦しくなってしまうと思います。
3) 水泳の授業直後、学校にドライヤーがなく髪を乾かせない。濡れた髪が服に当たって、服が濡れないようにタオルを肩や背中にかけるのも禁止。
髪の毛が長い女の子は、肩や背中あたりの服が濡れてかわいそうです。
私自身が子供だった昭和の学校では当たり前だったことも、令和の今では当たり前ではなくなってきました。昔に比べると、親御さんの意見があれば、改善を検討してもらいやすくもなっています。
今回は、小学校教師の仕事を続ける中で、不思議に思った小学校の謎ルールを紹介します。「先生の事情とホンネ」というテーマで連載させていただいてる本コーナーの趣旨にもぴったりだと思います。
【1】先生は、授業中に書いた黒板を消したらだめ
まず1つ目は、1時間(45分間)の授業で黒板に書いたことは、途中で消したらだめというルールです(もちろん、全国の小学校の先生方が、授業中に黒板を消さないわけではないですし、消したらだめだと言われているわけではありません)。このことは、知らない子供や親御さんも多いと思います。
黒板に書いたことを消してはいけない理由は、1時間の授業の流れがわかるようにするためです。黒板に書いた字を途中で消せないので、教師は黒板の端っこに字を書いたり、小さな字を書いたりしないといけません。文字と文字の行間も詰め詰めで書かないといけません。
教室の端のほうに座っている子供や、後ろの方に座っている子供は、黒板に書かれた字が見えにくいことがあります。文字と文字が重なって見えたり、揺れて見えたりするディスレクシア(読字障がい)の子供にとっても見えにくいです。また、学習意欲や学力が低い子供にとっても、小さな字でギュウギュウに黒板に書かれるよりも、大きな字でゆったりと書いてもらったほうが、理解もやる気も上がると思います)。
ただ、1時間の授業の流れは、ノートや教科書を見たらわかると思うのです。そして、そのためのノートや教科書だと思います。
私が、授業を客観的に見ていて、もっとも「わかりやすいな~」と感じた授業の黒板は、ALT(外国語指導助手)の先生による、外国語の授業です。そのとき、子供たちにとって必要なことだけを黒板の中央に大きく書くので、見やすいし、集中しやすいし、理解しやすく感じます。
【2】授業参観日や研究授業の時間だけ、スーツを着る
次の謎ルールは、普段の授業は、ジャージなどラフな格好でしているのに、保護者が来る授業参観や、同僚や外部から授業を見に来る研究授業がある時間だけ、スーツを着て授業をすることです。
ジャージ姿で普段、仕事をすることを決して否定したり批判したりしているわけではありません。むしろ、小学校の先生は、子供たちと遊んだり、体育や図工や習字の授業をしたり、せわしなく動き回ったりするので、ジャージなど動きやすい服装のほうが良いと思います。
では、小学校の先生は、なぜ授業参観や研究授業のときだけ、スーツに着替えるのでしょうか。その理由は、「みんなが着ているから」「学年主任が着ているから」「授業を大人に見てもらうから」「管理職にきれいめの恰好でと言われるから」などさまざま考えられますが、はっきりとした理由はわかりません。
私の息子と娘の保育園は異なりますが、どちらの保育園とも、毎回、参観日のときの先生方は普段通りのジャージ姿でした。もちろんその姿を見て違和感をもったことは1度もありませんでした。むしろ、学校の先生より普段どおりの姿を見せてくれていることに対して、信頼と信用の感情をもちました。
私自身が中学生で生意気盛りの頃、参観日のときだけ綺麗な格好をする先生に対して、
「どこ向いて授業してるねん。いちばん、気にせなあかんのは、俺ら生徒に対してやろ」
と言ってしまったこともあります…。
先生に対して偉そうなことを言った私自身が教師になった今、中学生の頃の自分に同じことを言われないように心がけています(もちろん、懇談会や家庭訪問のときは、スーツ姿です)。
【3】授業中、ハンドサインで子供たちに発表させる
3つ目は、授業中、子供たちが意見を発表したいときにあげる手の形です。
どんな手の形だと思いますか?
パーだけでなく、グーや、チョキの形で子供たちに手をあげさせるのです。
・パーで手をあげるときは、単純に意見を発表したいときです。
・チョキで手をあげるときは、誰かの発表に対して、付け足しがあるときです。
・グーで手をあげるときは、誰かの発表に対して「私も同じです」という意味があります。
(だから教師は、グーで手を挙げている子供を指名する必要はないのです)
これも全国の小学校でさせていることではありません。
このグー・チョキ・パーの授業中のハンドサインは、私自身が小学生のころは、体験したことがありませんでした。だから、教師になって初めて見たときは、驚きました。何をしているかわかりませんでした。そして、子供たちに聞いて教えてもらいました。
また若手教師だった頃、研究授業後の討議会で、子供が意欲的に授業中に発表する工夫について話しあっているとき、私は、
「中学・高校になったら、グーやチョキで手をあげて発表しません。大人もしません。私たち教師も職員会議や研修会では、パーの形で手をあげます。幼稚園や保育園もパーの手をあげて意見します。なぜ、小学生にだけ、ジャンケンみたいな形で手をあげさせるのですか? しゃべれない子供がいたら、ハンドサインを使う意味がわかるのですが…。チョキやグーでなく、言葉で『〇〇さんに、付け足しで』と言ったり、『〇〇さんと同じ意見です』と言ったり、自分の口でしっかり話すことができるようにしていくことが大事なんじゃないですか?」
と意見しました(同僚への敬意を大きく欠いた発言でした…)。
*後々、ハンドサインについて調べると、『熱中時代2、先生編』という1980年放送のテレビドラマで、出演していた水谷豊さんが演じる北野先生がさせていたことがわかりました。授業で自分の考えに自信がもてない子供たちへの工夫で、「自信がある」「自信がない」「わからない」などをハンドサインで全員の挙手をさせていました。
というわけで、今回は、教師目線で不思議だと感じたことのあるルールを3つ紹介させていただきました。
学校の謎ルールに疑問をもったことがあるのは、子供や親御さんだけでなく、学校の先生にもいることを知ってもらえたら嬉しいです。そして、「このルールは納得できない」「意味がわからない」などがあれば、ぜひ、教えていただきたいです。教師の仕事を長く続けるほど慣れてしまって、当たり前だと思うようになってしまうからです。
連載「先生の事情とホンネ」