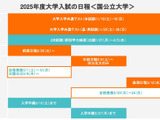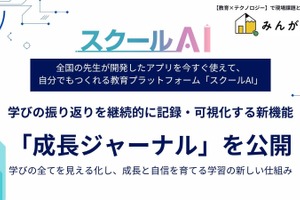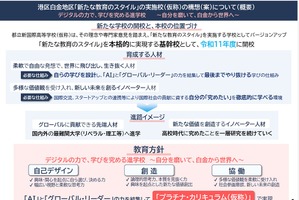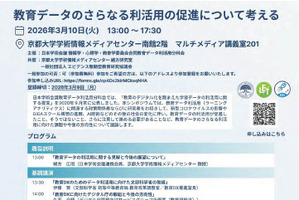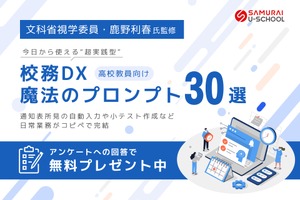教育現場でのAI利用に関して、多くの議論とともに導入と検証が始まり、校務の効率化への期待が高まっている。Microsoft 365 CopilotをおよびCopilot+ PCを校務で活用している、足立学園中学校・高等学校の杉山直輝先生、東京学芸大学附属小金井小学校の小池翔太先生の対談を行った。
杉山先生、小池先生ともに数多くの教育ICTサービスの導入と実践の経験をもち、ICTの活用により教育の質を向上することを目的にマイクロソフトが認定するMIEE(Microsoft Innovative Educator Expert、マイクロソフト認定教育イノベーター)としても活躍中だ。
Microsoft 365 Copilot
Microsoft 365 Copilotは、Microsoft 365と統合された有償の生成AIアシスタントツール。WordやExcel、PowerPoint、Outlook、TeamsなどのMicrosoft 365アプリで、資料の要約や下書き、データ分析、画像の生成などの日々の業務に使用できる。またユーザーと組織のデータを保護する機能を備えており、入力した情報は保存されず、AIモデルの学習に利用されることもない。
Copilot+ PC
通常のパソコンに内蔵されているパソコンを制御するCPUやグラフィック処理に使われるGPUに加え、AI処理に特化したNPU(Neural Processing Unit)を搭載。AI処理に特化したチップを搭載することで、従来の文書作成や会議などのタスクはCPU、AIの処理はNPUと負荷を分散でき、消費電力を抑えながらもパフォーマンスの向上が期待される。また、Copilot+ PCのキーボードには「Copilotキー」が搭載されており、このキーを押すことで、すぐにCopilotを起動することができる。

校務にMicrosoft 365 Copilotを導入した理由
小池先生:小金井小学校の教員のICT環境ですが、授業用にSurface Laptop Goを利用し、校務は別のPCと、2台持ちになっています。
杉山先生:足立学園の教員はSurface Proを利用しています。また私自身は現在Copilot+ PCも使っていますが、スペックが高くて使いやすいです。
小池先生:私も今、Copilot+ PCを使っていますが、バッテリー持ちが良いですよね。教員が日常的にハイスペックのPCで生成AIを利用できるのはとても助かります。足立学園さんが生成AIのCopilotを校務に導入したのには、どのような背景があったのでしょうか。
杉山先生:私たちは有償版のMicrosoft 365 Copilotを導入する前に、無償のCopilotを試していましたが、やはり有償版は性能も良くて、Word・Excel・PowerPointといった日常的に利用しているツールを横断的に使えることが、導入の大きな要因になりました。
小池先生:小金井小では昨年5月に、教養として生成AIに関する教員研修を実施しました。参加した先生方には、指導案のリライトや作成に使えることにメリットを感じた方が多かったようです。本校は今年度、文部科学省の最先端技術教育データ利活用実証事業に採択されて、その予算で生成AIと教育データを組み合わせて活用する目標を立て、全教職員35名に有償版のMicrosoft 365 Copilotのライセンスを付与しました。
足立学園さんでは、生成AIについて独自のガイドラインを作成されてますか。
杉山先生:ICTに関するガイドラインはありますが、現在のところAIに関しては作成していません。生成AIについては、導入を先行し、文部科学省のガイドラインに則って利用しているかたちです。
小池先生:私自身、文部科学省の「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」作成の際に、実践者枠で関わらせていただきました。それを校内で紹介し、今は足立学園さんと同様、このガイドラインに準じて利用しています。

生成AI導入はスモールステップで
小池先生:足立学園さんではMicrosoft 365 Copilotの導入準備をどのように進められたのでしょうか。
杉山先生:今年(2024年)の4月に、まずはAIに触れてみることを目的に教員研修をしてCopilotを紹介しました。導入した今年の8月には、ライセンスを付与する10名の先生方を、私が選ばせていただき、基本的な利用方法を紹介したうえで、使い始めてもらいました。
小池先生:小金井小でも導入した今年の8月に、マイクロソフトの協力で、有償版ならではの機能を学ぶオンライン研修を任意参加で実施しました。校務が忙しい時期にも関わらず半数以上の教職員が参加してくれました。杉山先生は10名を、どのように選抜されたのでしょうか。
杉山先生:各教科の先生方と、積極的に使ってくれそうな先生方、管理職の先生方から選びました。ただし8月の研修では、そのほかにも自ら希望して参加してくれた先生も数名いました。
小池先生:私たちは35名一斉に導入しましたが、視聴覚機器の管理をする情報部のコアメンバー6名とは月に1回の定例会議をしていました。やはりある程度、人数を絞ってスモールステップで導入することが大事かもしれませんね。足立学園さんは、全体で何人の先生がいらっしゃるのでしょうか。
杉山先生:現在は中高合わせて130名です。これまでも新しいサービスや機能を導入する際には、私から各教科に展開してきました。まずは、情報を届けて利用してもらい、評価してもらいます。良い評価が蓄積されると、教科会で共有します。すると教科の先生方の間で利用が広がっていきます。これは昔から同じやり方ですね。
小池先生:ICTの主任や情報担当になると、皆さんに使ってもらうために、指導案や事例集を作ってそれを元に進めるケースが多くなりますが、杉山先生は、お膳立てするのではなく、まずは先生方に使ってもらい、課題や利点を出してもらうというボトムアップのアプローチなんですね。
杉山先生:校務の効率化について感じるのは、生成AIを入れたから劇的に変わるというよりも、すべてで少しずつ時間短縮を積み重ねていくということです。先日も、FormsでのCopilot利用に関するアンケートを取ったところ、意外な発見がありました。それを共有すれば、おのずと活用する先生は増えていくと思います。

議事録、アイデアの壁打ちから学級経営の雰囲気作りまで
杉山先生:小金井小ではどのようにCopilotを利用されていますか。
小池先生:Teamsでオンラインの職員会議をしていますが、Copilotに議事録や要約、今後やるべきことをまとめてもらっています。先生方はここまでできるのかと本当に感動していました。職員会議の司会・記録は毎回学年の先生が持ち回りで担当していて、今は移行期ですが、そろそろ全面的にCopilotに任せても良いと考えているところです。Copilotは、発言者の情報も紐付けてくれるので、会議のあり方や議事録の取り方など、学校のルーティンを変えるきっかけになるかもしれません。
杉山先生:先程もお話ししたとおり、私はCopilot+ PCを使っていますが、オンライン会議はとても快適です。Windows Studio エフェクトのカメラ追尾機能はとても便利で、長時間の会議で同じ姿勢を維持するのが難しいときなど、動いても追ってくれるのはとても助かります。
小池先生:面白かったのは、ある教員が、運動会で「台風の目」というみんなで棒を持ってグルグル回るようなプログラムの名前を変えたいということになったときです。Copilotに「台風の目」に代わるかっこいい名前を10個あげてほしいと伝え、出てきた中から「旋風の覇者」を採用したようです。
仮に良いアイデアが出なくても、Copilotは第三者的なので、出てきた考えを否定しやすく、何度でも壁打ちしやすい点も良いですよね。放課後の職員室でゆるっとした話を、Copilotを入れて考えられたのは、とても面白い経験でした。
杉山先生:Formsで小テストや期末考査などの問題を作成するときに、これまでは自分の知識をもとにしてきましたが、Copilotは他者の視点を提案してくれるので助かっています。回答の選択肢を作成する場合も、Copilotが思いもよらないものを出してくれます。
小池先生:Formsで子供たちから授業の感想などを集めて、Copilotでどのような傾向があるのかを要約して把握することもあります。逆にCopilotに少数意見を抽出してもらえば、子供たちの多様な考えの可視化に役立ちます。たとえば、「Copilotの要約からこんな傾向がわかるけど、みんなはこの考えと同じだった?」「いや、僕は全然違うよ」といったやり取りにつながり、学級経営の雰囲気作りへの活用も考えられます。
AI×クラウドで実現する校務の効率化
杉山先生:最近、資料を探す際にTeamsでCopilotを使います。足立学園は学年やクラスごとに多くのチームやグループチャットがあるので、いつどこに上げた資料かを調べるときにCopilotを使います。内容的に近いものを抽出してくれるので、ひとつひとつのファイルを開いて確認する必要がなく、時間が大幅に短縮されています。
小池先生:Teamsを日常使いしている学校では、ファイルがさまざまな場所に点在しますよね。最近はファイルの中身をCopilotが把握してくれて探しやすくなっています。ほかの生成AIサービスだと、ファイルを外部サーバーにアップロードしなければならないので、セキュリティ的に危険です。Microsoft 365 Copilotならセキュリティの心配もなく、ファイルの内容を高速で調べてくれるので私も良く使っています。
GIGAスクールも5年目になり、クラウドにデータが蓄積されてきました。AIとクラウドデータを掛け合わせれば、ファイルの検索はもちろん、メールやチャットの見落としもCopilotに助けてもらえます。
杉山先生:文書や資料を作成する場合も、WordやPowerPointのCopilotに、昨年のものを参考にたたき台を作ってもらえば時間はかなり短縮できます。また、作成した文書をCopilotに校正してもらえば、ミスを防ぐこともできます。Copilotに確認してもらうことで、ほかの先生の手を煩わせることが減ったのも、大きなメリットです。

AIと共に学びを進めていく視点
小池先生:今後、Copilotに期待することはありますか。
杉山先生:Copilotに期待というより、我々が使い方を学ぶべきことが多いのではと感じています。私は最近常に、Copilotにこれは聞いても良いか、どう質問したら良いかと考えています。
小池先生:こうしたインパクトのあるAIがある今、主体的に学習に取り組む姿勢や学びに向かう力、協働的な学びなどを大人が子供に押し付けるのではなく、子供たち自身が本質的な問いを立ててCopilotをどう使っていくかを一緒に考えていきたいです。AIによって学びがより良くなる視点と、それに加えてAIと共に学びを進めていく視点。子供たちがAIと1対1ではなく、グループの中にAIがいるという学びのあり方を、教員がうまく導けたらと思います。
杉山先生:小池先生は今日、Copilotを使いましたか。
小池先生:子供たちに、Teamsに今日の音楽会の感想を書いてもらい、クラス全体で振り返りができるようCopilotに小2にもわかるように要約してもらいました。有償版ではMicrosoft 365アプリのあらゆる場所にCopilotがあるので、日常的に生成AIを使うハードルが下がります。
杉山先生:私のところに今日、高3の生徒が大学入試の面接の練習をしたいと言って来ましたが、Copilotに「●●大学のアドミッションポリシーを出して」と伝えるとすぐに出てきました。これまでは、生徒に印刷して持ってきてもらったり、教員が大学のサイトを調べてWordの書類を作ったりして準備をしてから、面接練習に入っていましたが、Copilotはそれこそ質問事項まで出してくれますので、かなりの時短になっています。
小池先生:Copilotを日常的に使うようになって、Copilot+ PCの速さや充電の持ちの良さも実感しているところです。今後は教員が生成AIを使って子供たちにさまざまなものを見せることも多くなると思います。そうしたときに子供たちと同じスペックのパソコンでは厳しい。もちろん、電源に繋げないこともありますので、Copilot+ PCの性能の高さはとても助かります。

足立学園中学校・高等学校と東京学芸大学附属小金井小学校では、学校が組織として生成AIを活用して効果を共有しながら、より良い教育の実現に向かっている。Copilotをフルに活用しているお二方からは、校務や授業での活用のアイデアが次々と溢れ出てきて、学校現場が大きな変革に直面していることが伺えた。多くの教育現場にその考え方や実践は参考になるのではないだろうか。
Microsoftの生成AI 明日から使えるCopilot依頼文(プロンプト)10ダウンロードはこちら※ボタンをクリックすると資料のダウンロードを開始します。