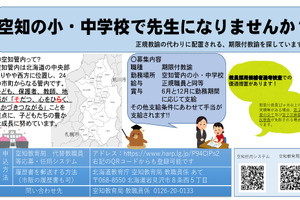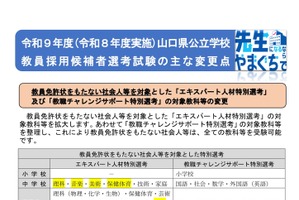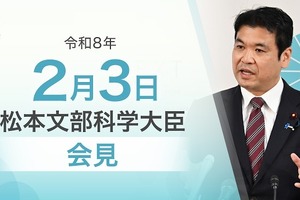通知表所見のコツ
学期末が近付いてくると、「そろそろやらなきゃ」と感じるのが通知表です。特に年度末は、他の事務作業も多く、じっくりと所見に取り組む時間がなかなか取れないという方も多いかもしれません。また、1人の児童に対して何度も所見を書くことになり、いつも似たような所見になってしまうということもあるでしょう。
そこで、所見を書くにあたって、先生方が悩みやすいと思われるタイプの児童を取り上げます。今回は、「平均タイプの子」の所見についてご紹介します。
「平均タイプの子」とは?
所見を書く際、意外と内容に悩みやすいのが、「平均タイプの子」ではないでしょうか。それは、何でも器用にこなす優等生タイプの子や、いつも手がかかる課題の多い子のほうが先生の目につきやすく、所見のネタも多く把握できているからです。
「平均タイプの子」とは、
・特に目立った得意科目や特技がない
・テストの点数は100点ではないけれど、70点以下でもない
・毎回挙手するグイグイ型ではないけれど、まったくアピールしないわけでもない
・リーダー格ではないけれど、1人ぼっちで過ごしているわけではない
というような児童です。
視点を変えよう
「平均タイプの子」と表現していますが、これは「何の」平均なのでしょうか。また、「誰が」平均と判断しているのでしょうか。実は、この「平均タイプの子」というとらえ方の裏側には、先生の考え方が表れています。「集団の中の1人」「集団の中でどの位置にあるか」という視点で子供を見ているということです。
学習集団・生活集団としてとらえる場面はもちろんありますが、ひとりひとりの成長を見つめられるようにしましょう。
「平均タイプの子」所見のポイント
結果ではなくプロセスを記述する
どのように考えて答えを出したのか、どんな活動で主体的になったのか、完成に至るまでどんな試行錯誤をしたのか等、プロセスに注目してみましょう。
<例>
「面積を求める問題に取り組んだ時には、今まで学習したことを活かせるように、図形を回転させたり補助線を引いたりと、試行錯誤していました。」
「工作ではさまざまな箱を重ねたり向きを変えたりして、自分のイメージした形に近づけられるよう工夫していました。」
「面積を求める問題に取り組んだ時には、今まで学習したことを活かせるように、図形を回転させたり補助線を引いたりと、試行錯誤していました。」
「工作ではさまざまな箱を重ねたり向きを変えたりして、自分のイメージした形に近づけられるよう工夫していました。」
その子が変化したきっかけを記述する
何かができるようになったきっかけ、新しいことに関心をもったきっかけ等、児童の心が大きく動いた瞬間を記述しましょう。
<例>
「国語の物語文で扱ったことをきっかけに、重松清さんの本に関心をもつようになりました。図書室で本を借りることが増え、今でさまざまな著者のシリーズものを読むようになりました。」
「天気の移り変わりについての映像を見たときには、教室から見える空もちらちらと見ており、映像と実際の空を見比べているようでした。また、空のいろいろな方向を見上げる姿や、天気についてのタブレットで調べる姿が何度も見られました。」
「国語の物語文で扱ったことをきっかけに、重松清さんの本に関心をもつようになりました。図書室で本を借りることが増え、今でさまざまな著者のシリーズものを読むようになりました。」
「天気の移り変わりについての映像を見たときには、教室から見える空もちらちらと見ており、映像と実際の空を見比べているようでした。また、空のいろいろな方向を見上げる姿や、天気についてのタブレットで調べる姿が何度も見られました。」
学校ならではのようすを記述する
個人面談等を通して、児童のご家庭でのようすがわかるようでしたら、ご家庭と異なる児童のようすを積極的に伝達しましょう。保護者の方は、「家ではまだまだ幼いけれど、学校ではこんなにがんばっているんだ」と感じるはずです。
<例>
「委員会の当番・給食当番・日直が重なったことがありました。何を優先すべきか考え、日直の代理を友達に頼む等、見通しをもって行動する力がついてきています。」
「校庭で遊んでいると、1年生が転んで泣いていることに気付き、保健室まで連れて行っていました。『上級生になったんだ』という自覚が感じられます」
「委員会の当番・給食当番・日直が重なったことがありました。何を優先すべきか考え、日直の代理を友達に頼む等、見通しをもって行動する力がついてきています。」
「校庭で遊んでいると、1年生が転んで泣いていることに気付き、保健室まで連れて行っていました。『上級生になったんだ』という自覚が感じられます」
他の児童との関わりが想像できるように記述する
保護者が児童について気になることの1つが、「友達とうまくやれているか」です。学習面について伝えるときにも、他の児童との関わりがわかるように記述してみましょう。
<例>
「主人公の気持ちについて話しあったときには、○○さんの発言に対して『自分には思いつかなかった』『そこまで深く考えているのがすごい』という声が挙がりました。そこから、自分の考えを表現することに自信がついてきたようです。」
「リレーでは、走るのが遅いことを気にしている子に『みんなでがんばるから大丈夫だよ。』『何番目が良い?』と優しく声をかけていました。レースでは負けてしまいましたが、もっとも絆が深まったチームです。」
「主人公の気持ちについて話しあったときには、○○さんの発言に対して『自分には思いつかなかった』『そこまで深く考えているのがすごい』という声が挙がりました。そこから、自分の考えを表現することに自信がついてきたようです。」
「リレーでは、走るのが遅いことを気にしている子に『みんなでがんばるから大丈夫だよ。』『何番目が良い?』と優しく声をかけていました。レースでは負けてしまいましたが、もっとも絆が深まったチームです。」
今回は「平均タイプの子」の所見についてご紹介しました。何について書こうか迷ったら、1日その子に注目して過ごしてみてください。今まで気づかなかった一面が見えてくるかもしれません。次回は「課題が多い子」の所見について、ご紹介します。
幸島 由起子
 塾講師として3年間勤めたのち、東京都公立小学校にて15年間勤務。1,500人以上のお子さん・保護者の方と関わり、成長を見守ってきた。担当した学年のお子さんに合わせてカリキュラムマネジメントをするのが好き。担当していた校務分掌は、学年主任・特別活動主任・学校図書館・特別支援コーディネーター等。現在は、教員採用試験の論作文の指導や添削、子供への指導法に関する研修講師をしながら、今後に向けて心理学や子育て支援について学びを深めている。自身も小学生と保育園児の子育て中。
塾講師として3年間勤めたのち、東京都公立小学校にて15年間勤務。1,500人以上のお子さん・保護者の方と関わり、成長を見守ってきた。担当した学年のお子さんに合わせてカリキュラムマネジメントをするのが好き。担当していた校務分掌は、学年主任・特別活動主任・学校図書館・特別支援コーディネーター等。現在は、教員採用試験の論作文の指導や添削、子供への指導法に関する研修講師をしながら、今後に向けて心理学や子育て支援について学びを深めている。自身も小学生と保育園児の子育て中。