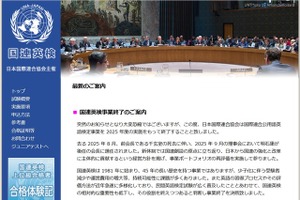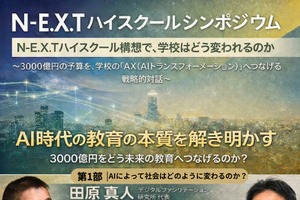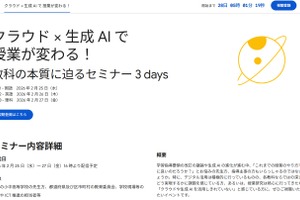学校に寄せられるさまざまな相談やクレーム。保護者や地域からの相談に先生はどのように対応するのが良いだろうか?クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第227回のテーマは「休み明けに学校へ行くのを渋る」。
休み中に生活リズムが崩れやすい
大人も子供も「5月病」と呼ばれるものがあります。新しい環境に慣れてきた時期に疲れなども溜まり、学校や職場へ足が向きにくくなる状態です。以前もこの話題を書いたことがあるので、今回は以前はあまり話題にしなかった「生活リズムを整える」というテーマで書いていきたいと思います。
休み明けに心身ともに少しテンションが下がった状態になるということは、どの時期でも起こるものです。日本では新年度が始まり、1か月経ったタイミングでゴールデンウィーク(GW)があります。先ほども書いたように心身ともに疲れが溜まっていることなどと関連し、このタイミングで不適応を起こしやすいのは事実です。
ただ、通常の授業期間であっても、休み明けの月曜日は何となくダラダラとした感じになってしまう学級は少なくありません。これはGWほどではないですが、休み(土日)の間に、生活のリズムが崩れてしまったことが関係していることが多いです。
子供が学校に行くのを嫌がるという状況では、その原因は1つではなく、いくつものの原因が重なり合い、関係し合っていることが多いです。学校に関係するものでは、友達関係がうまくいっていない(いじめられている)、勉強がわからない、テストが不安、給食が苦痛、体育の授業が嫌いなどです。学校としてはこういった要因を減らすべく努力をしていくのはもちろんです。
家庭が原因となっている場合もあります。たとえば、夜遅くまでゲームをしたり動画を見たりしている、休みの日に遠くまで出掛けて帰ってくるのが日曜日の遅い時間になってしまった、スポーツチームに属しており土日の練習や試合で疲れが溜まっているなどです。
生活リズムを整える
子供の心身が良好な状態であれば、少しの負荷がプラスに働く場合もあります。しかし、そういった負荷がさらに悪い形で子供に影響しているような場合は考えていく必要があります。学校(担任)の立場としては、学校ができることはしていくということを伝えたうえで、家庭でも子供の状態を見ながら、変えられる部分は変えていってほしいと伝えていくと良いでしょう。
こういった際に特に重要になるのが「生活リズム」です。休みになっても「早寝・早起き」のリズムが崩れない子供は、そういった点でトラブルの発生源を1つ減らすことができていることになります。何か他に嫌なことがある状況で、そのうえで生活のリズムが崩れると、そのことがきっかけとなり、意欲の低下などにつながります。
「睡眠」は、マズローの欲求段階説というもので、もっとも下位にある「生理的欲求」です。人が何かに取り組もうとする際、はじめに満たされることが望ましいとされているものです。「生理的欲求」には、「睡眠」の他、「食事」があります。きちんと朝ご飯を食べることなどです。昔から言われている「早寝・早起き・朝ご飯」は、家庭での生活リズムに関することです。こういった部分の重要性を親に伝えていくことが大切でしょう。
本企画では、読者の皆さまからの質問を受け付けています。下記のボタンをクリックして表示されるフォームより送信ください。実際に学校へ寄せられた相談のほか、保護者が学校へ伝えた相談など、鈴木先生に対応方法を聞いてみたい相談事例を募集します。
質問をする